はじめに
小学校高学年(4年生後半〜6年生)になると、子どもは心身ともに大きく成長します。しかしその反面、不登校が増え始める時期でもあります。この時期に不登校が始まる背景には、思春期特有の変化や人間関係の複雑化、学習への不安などが深く関わっています。
今回は、小学校高学年の不登校に特化して、特徴・原因・支援のポイントをわかりやすく解説します。
小学校高学年に不登校が増える理由とは?
1. 思春期の入り口による情緒の不安定さ
- 自己意識が強くなり、「友達にどう見られているか」が気になるように
- 自分の感情をうまく表現できず、ストレスを内にため込む
- 親への反発や距離感も出てくる
2. 友人関係が複雑化
- 高学年になるとグループの固定化や“仲間外れ”が起きやすくなる
- SNSやゲームなどでのトラブルも影響
- 無視や陰口など、表に出にくいいじめの兆候も
3. 学習の壁にぶつかる
- 算数の文章題や国語の読解など、抽象的な内容が増加
- 「ついていけない」不安や劣等感が強まる
- 発達障害や学習障害がこの時期に表面化することも
よく見られるサイン・行動
小学校高学年の不登校は、ある日突然ではなく、**「登校しぶり」**から始まることが多いです。次のような兆候が見られたら注意しましょう。
- 「お腹が痛い」「頭が痛い」と頻繁に訴える
- 朝になると布団から出られない
- 休日や夕方は元気でも、登校日の朝だけ元気がない
- 学校の話題を避ける、話したがらない
- 宿題や学習に強い拒否反応を示す
- イライラが増え、兄弟や親に当たるようになる
保護者・支援者にできること
1. 「無理やり行かせる」はNG
高学年の不登校は、本人の自尊心や社会性の基盤に大きな影響を与えます。「行けば何とかなる」と無理に登校させるのではなく、「なぜ行けないのか」を一緒に考える姿勢が重要です。
2. 話を聴く時は“否定しない”
- 「そんなことで休むの?」という言葉はNG
- 「どうしたの?」「つらかったね」と共感する
- 会話の主導権は子どもに持たせ、ゆっくり聞く
3. 安心できる居場所づくり
- 家では“学校に行かない自分”を責めなくていい環境を作る
- 図書館や地域のフリースペースなど、安心して過ごせる場所を見つける
- オンライン授業や家庭学習を通じて、学びを止めない支援も検討
支援のプロに相談するタイミング
以下のような場合は、専門機関に早めに相談することが望ましいです。
- 1か月以上学校に行けない日が続いている
- 身体症状(腹痛・頭痛・不眠など)が強く出ている
- 発達特性や学習障害の可能性を感じる
- 親子でどう関わればよいか分からなくなっている
→ 学校のスクールカウンセラーや教育相談センター、児童精神科、作業療法士などの専門職が支援してくれます。
まとめ
小学校高学年の不登校は、単なる「わがまま」や「甘え」ではありません。成長と変化の真っ只中で、子どもなりに必死にSOSを出しているのです。
早期に気づき、共感し、寄り添うことが回復への第一歩となります。
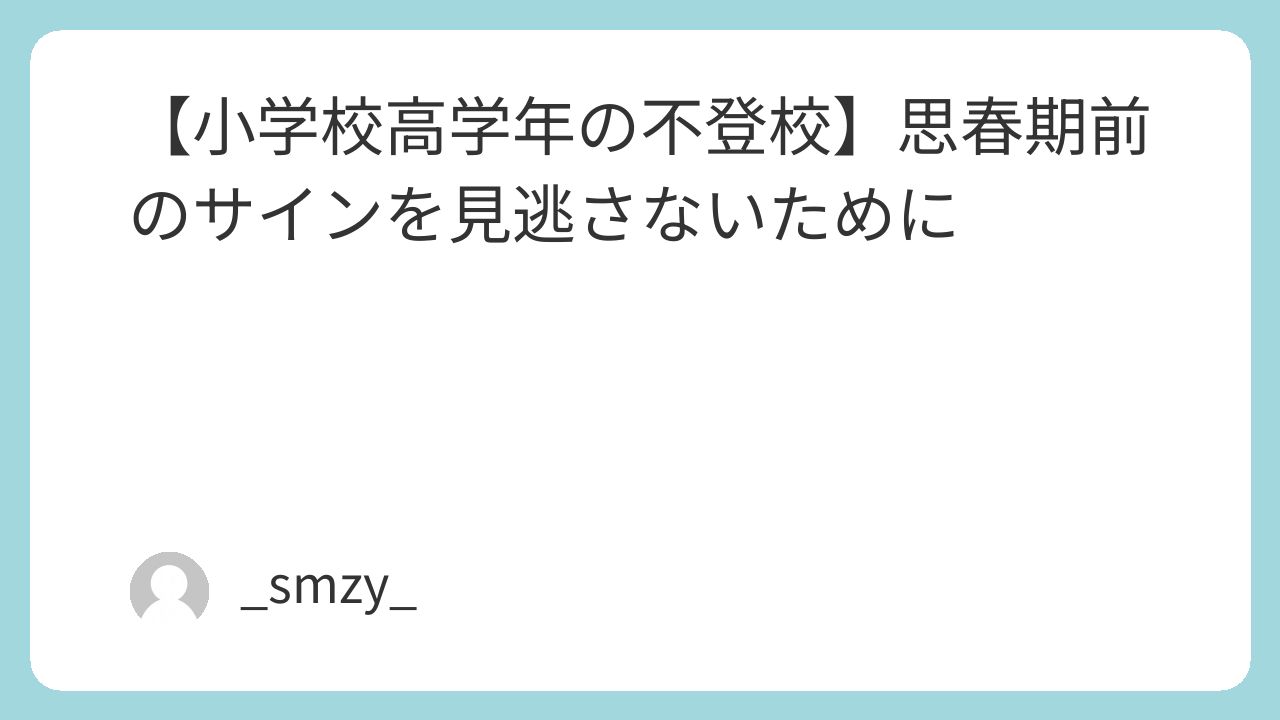
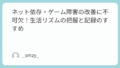
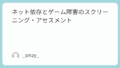
コメント