「うちの子、スマホを取り上げると激しく怒るんです」「朝までゲームをして寝ない」
そんな子どもの様子に、心配していませんか?
今、スマホやゲームの長時間使用が原因で、子どもが現実の生活に支障をきたす「ネット依存」が増えています。
本記事では、ネット依存の定義・原因・脳への影響・初期サイン・家庭でできる対策について、専門的な視点からわかりやすく解説します。
保護者の方が今日からできること、見直せることがきっと見つかります。
ネット依存とは?スマホやゲームがやめられなくなる仕組み
ネット依存とは何か?脳の仕組みやスマホ・ゲームがやめられなくなる背景を、ICD-11と最新の科学的視点で解説します。
ネット依存の定義(ICD-11より)
世界保健機関(WHO)は2019年、ゲーム障害(Gaming Disorder)を正式な疾患として分類しました。
これは「ゲームやSNSなどの利用を自分で制御できず、生活に支障が出ている状態」を指します。
依存が起こる脳のメカニズム(ドーパミン)
- ゲームやSNSは脳の「報酬系(ドーパミン系)」を刺激します。
- 成功・達成・通知・『いいね』などの刺激が、快感と結びつき、繰り返しを生みます。
- 結果として、現実生活よりもネット世界の方が魅力的に感じてしまうのです。
スマホ依存の子どもに見られる5つの初期サイン
スマホ依存の兆候を見逃さないために、保護者が知っておくべき5つの初期サインを具体例とともに紹介します。
- 時間感覚の喪失
「5分だけ」と言いながら3時間経ってしまうなど。 - 家族や友人との会話を避ける
外出や会話を嫌がり、画面の世界に閉じこもる傾向。 - 基本的な生活が乱れる
食事や睡眠、入浴を後回しにする。 - 感情のコントロールが効かなくなる
スマホを取り上げると激しく怒る・泣く・暴れる。 - 学校や習い事への関心が薄れる
登校しぶりや不登校につながることもあります。
なぜ子どもはスマホにハマるのか?|4つの背景
子どもがスマホに夢中になる背景には、心理的・家庭的な理由があります。4つの要因を詳しく解説します。
1. 現実生活での満足感の不足
学校生活でのストレス、成功体験の少なさ、親との関係が希薄な場合、ネットが逃げ場になります。
2. 承認欲求とランキング・通知依存
SNSの「いいね」、ゲームのランキングや報酬で承認を得る快感があります。
3. 時間制限のない環境
ルールがなければ、欲望のままに無制限に使用してしまいます。
4. 親のスマホ依存・家庭の無関心
親もスマホに夢中になっていませんか?親の背中を見て育つことを忘れずに。
家庭でできるネット依存対策5つのステップ
ネット依存の対策は家庭から。親子で取り組める5つの実践的なステップを紹介します。
1. 否定せず、まず話を聴く
「やめなさい!」では逆効果。まずは「どうして見たいのか」を理解しましょう。
2. 一緒にルールを作る
使用時間・使用場所・時間帯のルールは、親子で話し合って決めると守りやすくなります。
3. 日常の楽しさを増やす
運動、外遊び、家族とのレジャーなど、現実世界の「楽しいこと」を増やしましょう。
4. 家族全体のネットの使い方を見直す
大人も一緒に使い方を見直すことで、子どもに説得力が増します。
5. 必要なら専門機関に相談を
- 生活に支障が出ている場合は、児童精神科や作業療法士への相談をおすすめします。
- 早めの対応が、悪化を防ぐカギになります。
まとめ|「やめさせる」より「一緒に考える」姿勢が大切
ネット依存の子どもへの対応で大切なのは「否定」ではなく「共感」。家庭でできる支援の第一歩をまとめました。
ネット依存は意志の弱さではなく、心のSOSであることも少なくありません。
叱る・取り上げるだけでは解決せず、親子の信頼関係と対話がカギとなります。
家庭の中でできることから一歩ずつ始めてみましょう。
ご相談受付中
作業療法士として15年、ネット依存・不登校の支援経験があります。
お子さんのスマホ・ゲーム依存が心配な方は、コメント欄やお問い合わせからお気軽にご相談ください。
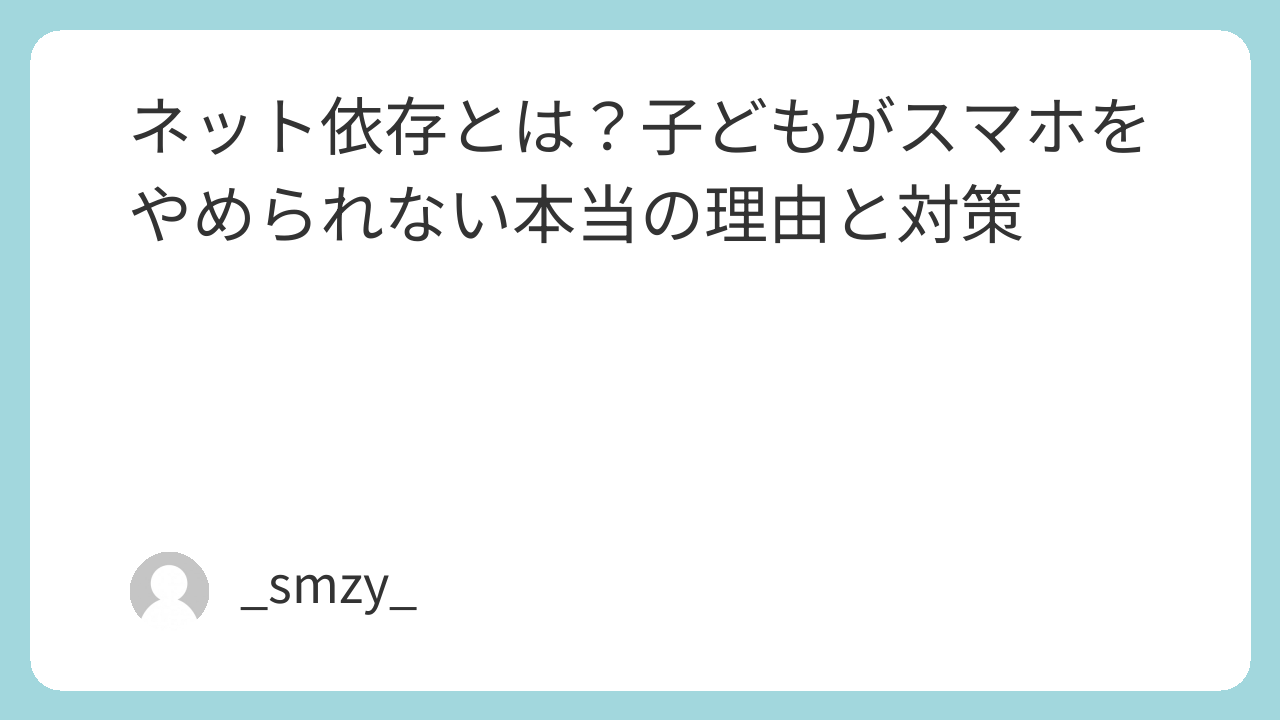
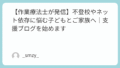
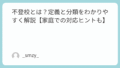
コメント