使用時間とコンテンツの分析がカギ!
ネット依存やゲーム障害の対応において、スマホやパソコンの「使用時間」と「利用しているコンテンツの内容」を分析することは非常に重要です。この記事では、家庭でも実践できる記録方法と、分析のポイントを紹介します。
なぜ「使用時間」と「コンテンツ分析」が重要なのか?
ネット依存の影響は、ただ単に「何時間使っているか」だけで決まりません。
たとえば:
- 30分間、英語の学習動画を見ている
- 深夜2時までオンラインゲームに課金してプレイしている
この2つでは、同じ30分でも心身への影響は全く異なります。
そのため、「何時間使ったか」と「何をしていたか」の両方を把握する必要があります。
ステップ1:使用時間を記録する
まずは客観的に使用時間を記録しましょう。おすすめのツール:
- iPhoneの「スクリーンタイム」機能
- Androidの「デジタルウェルビーイング」機能
- PC利用なら「RescueTime」や「ActivityWatch」など
記録すべきポイント:
- 曜日ごとの使用傾向(平日と休日)
- 深夜の使用時間の有無
- 勉強や食事、入浴など日常生活への干渉
ステップ2:利用コンテンツの内容を分類・分析
次に、「どんなアプリやサービスを使っていたか」を記録します。
分類の一例:
- SNS(Instagram、X、TikTokなど)
- 動画視聴(YouTube、Netflixなど)
- ゲーム(オンライン/ソーシャル/課金系)
- ショッピング(Amazon、楽天など)
- 通話・チャットアプリ(LINE、Discordなど)
- 調べもの、学習、趣味系
この分析を通して、使用目的が「娯楽」「ストレス解消」「人とのつながり」「暇つぶし」「逃避」など、何を満たしているのかが見えてきます。
ステップ3:記録をどう活かすか?
記録と分析から見えてくる課題に応じて、以下のような対処法を検討します。
- 使用時間の上限を設定する
- 通知オフやアプリ削除で物理的制限をかける
- 外遊びや読書などの代替行動を用意する
- 夜の使用時間が長い場合、睡眠・生活リズム改善へ
まとめ
ネット使用時間とコンテンツ内容を記録し分析することで、ネット依存の傾向やリスクを早期に発見できます。
支援者や保護者は、「使いすぎてる!」と一方的に注意するのではなく、「この時間に何をしていたか」を一緒に見ながら、理解と対話を重ねることが大切です。
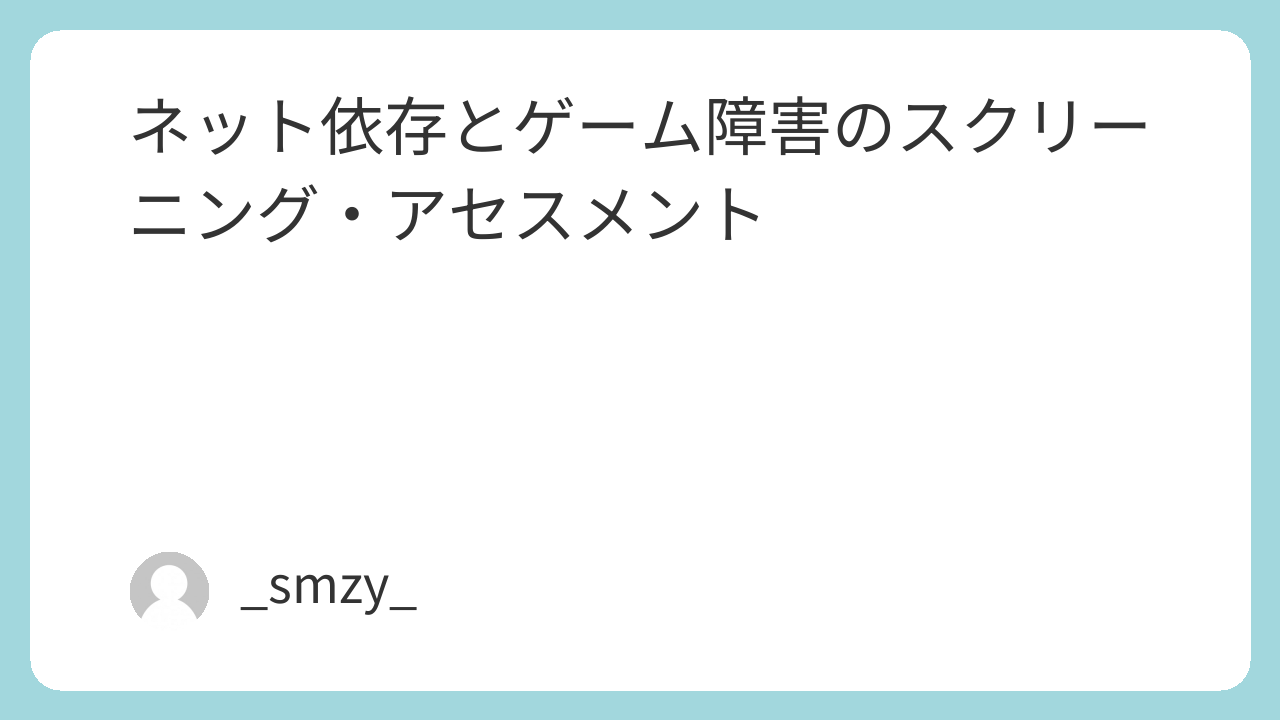
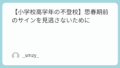
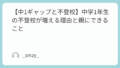
コメント