近年、子どもや若者の「ネット依存」が社会問題として注目されています。オンラインゲーム、SNS、動画視聴などの過剰利用は、生活リズムの乱れや学業不振だけでなく、心身の健康にも深刻な影響を及ぼします。その背景には、単なる習慣や嗜好だけではなく、小児期逆境体験(ACEs)が関わっているケースが少なくありません。今回は、ネット依存とACEsの関連について、脳科学と心理学の視点から掘り下げます。
1. ネット依存とは何か
ネット依存は、インターネットやデジタルデバイスの使用が生活全般に悪影響を及ぼしても使用をやめられない状態を指します。特徴的な症状には次のようなものがあります。
- 使用時間のコントロールが効かない
- 現実世界の活動や人間関係の回避
- やめると強い不安やイライラ(離脱症状)
WHOは2022年に「ゲーム障害(Gaming Disorder)」を国際疾病分類(ICD-11)に追加しており、ネット依存の深刻さが国際的にも認識されています。
2. ACEsとネット依存のつながり
ACEsを経験した子どもは、しばしば安心感や自己肯定感の不足、ストレス耐性の低下を抱えます。ネットの世界は、現実では得られない次のような要素を提供します。
- 自分のペースで関われる安全な「場」
- 承認や達成感を簡単に得られる仕組み
- 嫌な現実から離れられる逃避先
脳の報酬系(ドーパミン回路)は、現実よりも強い刺激をネットから受け続けることで依存状態に傾きやすくなります。ACEsにより脳の自己調整機能が弱まっている場合、そのリスクはさらに高まります。
3. ネット依存がもたらす二次的影響
- 睡眠不足 → 学習能力や感情コントロールの低下
- 運動不足 → 体力低下や肥満
- 家族・友人との関係悪化 → 孤立感の増大
これらは、もともとACEsによって脆弱になっている心身の健康に二重の負担をかけます。
4. 支援の方向性
ネット依存を単に「やめさせる」ことに集中すると、子どもの心の支えを奪ってしまう危険があります。大切なのは、
- 安全で信頼できる人間関係を築く
- ストレスを解消できる現実世界の活動を増やす
- 睡眠や食事など生活リズムを整える
といった「代替手段」と「基盤づくり」です。
関連書籍
『スマホゲーム依存症』
ネット・スマホ依存研究の第一人者による解説書。依存のメカニズムから治療・予防法まで幅広く紹介。
→ Amazon 楽天
『スマホ脳』(アンデシュ・ハンセン/新潮新書/2020年)
脳科学の観点から、スマホやネットが人間の脳に与える影響を解説。依存を抜け出すための具体的なヒントも掲載。
→ Amazon 楽天
『インターネット依存症からの回復』
医療現場での治療経験をもとに、ネット依存症の診断・治療・家族支援まで網羅した専門書。
→ Amazon 楽天
まとめ
ネット依存は、単なる遊びすぎや意思の弱さではなく、ACEsなど過去の逆境体験と密接に結びついていることがあります。背景にある「心の空白」に目を向け、依存行動の裏にあるニーズを理解することが、回復への第一歩です。
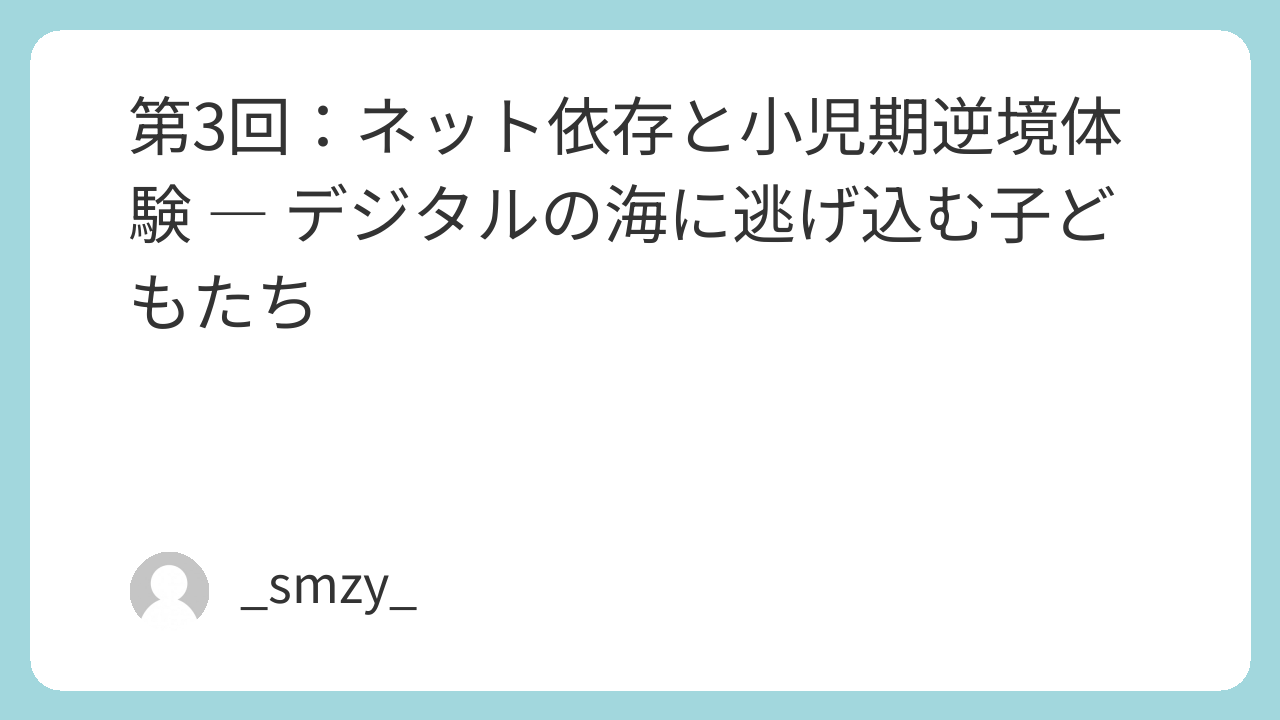



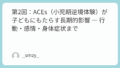
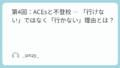
コメント