はじめに
ACEs(Adverse Childhood Experiences:小児期逆境体験)とは、子ども時代に経験する心理的・身体的ストレス要因のことです。
代表的な10項目には、虐待(身体的・心理的・性的)、ネグレクト、家庭内暴力、親の精神疾患や依存症、離婚・別居などが含まれます。
近年の研究では、ACEsが多いほど脳の発達・免疫機能・ホルモンバランスに影響が及び、将来的な心身の不調や社会適応の難しさにつながることが明らかになっています。
特に子どもの場合、ACEsは感覚処理・自己調整・学習意欲・対人関係など、日常のあらゆる場面に影響します。
作業療法士(OT)は、こうした子どもたちが生活の中で安全・安心を取り戻し、できることを少しずつ増やすための実践的サポートを行います。
1. ACEsと子どもの特性
ACEsの影響は一人ひとり異なりますが、作業療法の現場では次のような傾向が見られます。
- 感覚の過敏または鈍麻
大きな音に極端に驚く/痛みや寒さに鈍感になる - 情緒の不安定さ
ちょっとした出来事でパニックになる/急に黙り込む - 集中力の低下
机に向かっていられる時間が短い - 身体の緊張状態
肩や背中が常にこわばっている/浅い呼吸 - 予測不能への不安
予定が急に変わると混乱する
これらは「性格」や「わがまま」ではなく、脳と神経系が過去のストレスに適応した結果として現れる反応です。
2. 作業療法士ができる4つのアプローチ
(1) 感覚統合(Sensory Integration)
感覚統合は、脳が視覚・聴覚・前庭感覚(バランス)、固有感覚(筋肉や関節の感覚)などを整理し、適切に反応できるよう促す方法です。
- ブランコ、トランポリン、バランスボードで前庭感覚を刺激
- 重たいボールを押す・引く動きで固有感覚を活性化
- 感覚過敏な場合は、静音イヤーマフ・柔らかい照明・アロマなどで環境調整
ポイント:感覚統合は遊びの中で行うと効果が高く、子どもが「楽しい」と感じられることが大切です。
(2) 日常生活動作(ADL)の構造化
生活習慣の乱れはACEs経験児に多く見られます。
- 朝の支度、着替え、食事、片付けを視覚スケジュールで見える化
- タイマーを活用し、「あと○分」で次の行動に移れるよう促す
- 1ステップずつ教え、成功を繰り返す
小さな生活の成功体験は、自己肯定感の回復に直結します。
(3) 自己調整スキル(Self-regulation)の獲得
ACEsを経験した子どもは、交感神経が優位になりやすく、落ち着きを保つことが難しい場合があります。
- 呼吸法(4秒吸って、6秒吐く)
- 体ほぐし運動(肩回し、前屈)
- 感情温度計や「いまの気持ちカード」で気分を言語化
- 安心できる場所や物(クッション、ぬいぐるみ)を活用
感情の波を自覚することが、衝動やパニックの予防につながります。
(4) 家族・学校・地域との連携
OT単独の支援では限界があるため、多職種・多機関連携が重要です。
- 保護者に家庭での声かけ例や遊び方を提案
- 学校に感覚・情緒面の配慮事項を共有(例:静かな休憩場所の確保)
- スクールカウンセラー、心理士、福祉職と定期的な情報交換
連携がうまくいくと、子どもの支援が「点」から「面」へと広がります。
3. 支援の実例
- ケースA:感覚過敏で教室に入れなかった小4男児
→ OTセッションで前庭感覚遊びと呼吸法を習得。2か月後、短時間登校が可能に。 - ケースB:生活リズムが乱れ昼夜逆転していた中2女子
→ 視覚スケジュールとタイマーで朝の支度を定着化。半年で朝から登校できる日が増加。
まとめ
ACEsを抱える子どもへの作業療法は、「トラウマを治す」というより、安全な体験を積み重ね、自己調整力と生活スキルを回復させることが目的です。
作業療法士は、感覚・身体・生活のすべてを見渡し、子どもが安心して挑戦できる場を作る専門職です。
支援のカギは「できるようにする」だけでなく、「安心してできるようにする」こと。
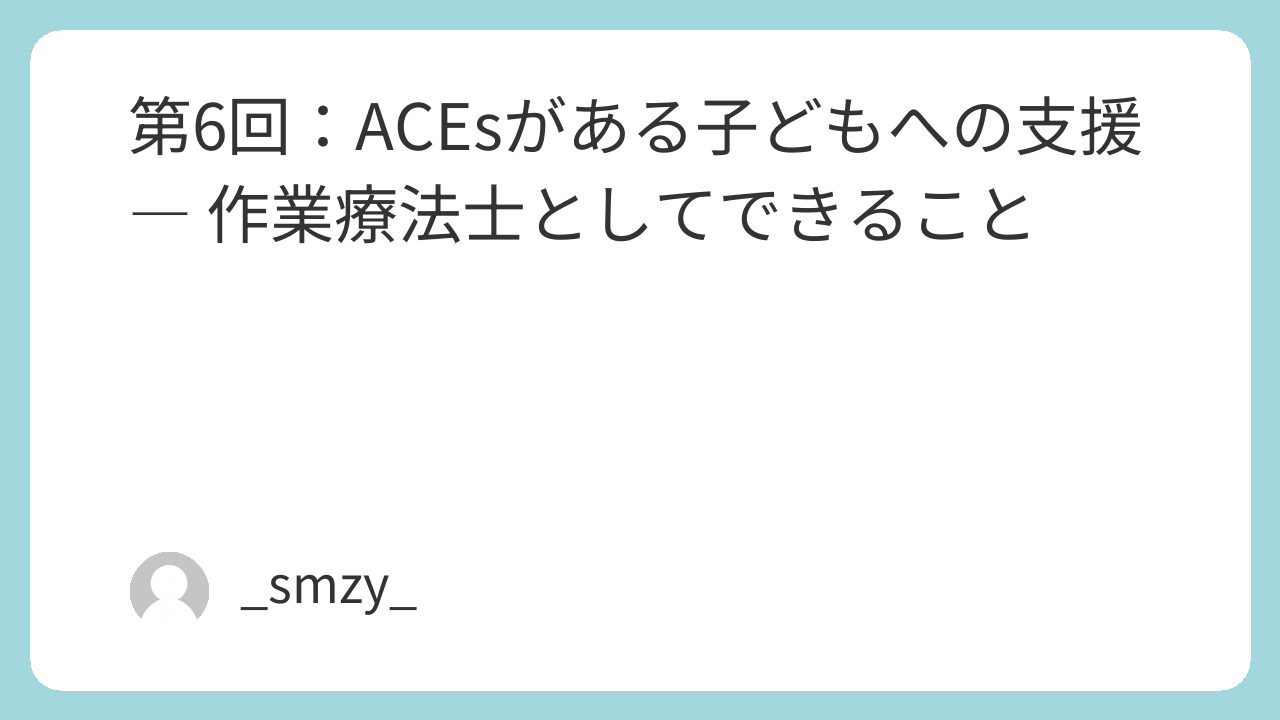
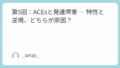
コメント