自閉症スペクトラム(ASD:Autism Spectrum Disorder)の症状は、大きく以下の2つのカテゴリーに分けられます:
① 社会的コミュニケーションや対人関係の困難
これは「人と関わることが苦手」とされる特性です。ただし、まったく関われないわけではなく、「やり方」がちょっと違う、というイメージです。
主な症状の例:
- アイコンタクトが少ない、または避ける
- 表情や身ぶりなどの非言語的なサインを読み取るのが難しい
- 相手の気持ちや暗黙のルールを理解するのが苦手
- 一方的に話し続けてしまう(会話のキャッチボールが苦手)
- 空気を読まずに発言したり、突然話題を変えてしまう
💡 解説ポイント:
こうした特徴のある方は、「他人に興味がない」のではなく、「どう関わればよいか」がわかりにくいだけなのです。
② 限定された興味・行動パターン、こだわりの強さ
もう一つの特徴が「決まったやり方」や「特定のもの」への強いこだわりです。
主な症状の例:
- 毎日のルーティンが崩れると強い不安を感じる
- 特定の物やテーマに強い興味(例:電車、昆虫、地図など)を持ち、詳しく調べたり話したがる
- 手をひらひらさせる、ぐるぐる回るなどの同じ動きを繰り返す(自己刺激行動)
- 音、光、におい、肌触りなどに過敏または鈍感(感覚の過敏・鈍麻)
💡 解説ポイント:
こだわりや繰り返しの行動は、不安を和らげる「安心の手段」であることが多く、無理にやめさせるのではなく「なぜそれをしているのか?」に注目することが大切です。
その他によくある特徴
- 集団行動が苦手、突然パニックになる
- 音読や文字の読み書きは得意でも、会話がうまくできない
- 年齢相応の「ごっこ遊び」や想像力を使った遊びが苦手
- 急な予定変更で混乱する
症状の現れ方は「人それぞれ」
ASDは「スペクトラム=連続体」という名前がついているように、症状の強さや現れ方は一人ひとり違います。
- ほとんど困りごとが見えにくい「軽度」の場合もあれば、
- 日常生活に大きな支援が必要な「重度」のケースもあります。
知的発達の遅れの有無によっても、支援の内容は変わってきます。
周囲ができる配慮とは?
ASDのある人の困りごとは、本人の「努力不足」ではなく、「情報の受け取り方や考え方の違い」によるものです。そのため、周囲のちょっとした配慮が大きな支えになります。
たとえば:
- 「曖昧な表現」を避けて具体的に説明する
- 急な予定変更は事前に伝える
- 感覚過敏に配慮した環境を整える(イヤーマフ、静かな場所の確保など)
- 強みを活かせる活動を取り入れる(好きな分野を活かした学習や仕事)
自閉症スペクトラムをもっと深く知るためのおすすめ書籍【今すぐ購入可能】
ここでは、自閉症スペクトラムに関心をもつ保護者・教育者・支援者の方におすすめの書籍を3冊ご紹介します。どれもAmazonや楽天ブックスなどで今すぐ購入できます。
① 『発達障害大全 ―「脳の個性」について知りたいことすべて』
著者:黒坂 真由子
ASDを含む発達障害について、最新の知見をもとにわかりやすく解説しています。脳科学の視点に加え、日常生活の困りごとへの支援方法も掲載されており、家族や支援者の入門書としても最適です。 Amazon 楽天
② 『自閉スペクトラム症の子どもを理解し支援する本』
田中哲 (監修), 藤原里美 (監修)
発達障害支援の第一人者である精神科医が、ASDの子どもたちが感じている世界や心の内面を丁寧に解説。実際の支援場面や療育の方向性についても実例をもとに紹介されており、現場感覚が得られます。Amazon 楽天
③ 『うちの子、発達障害かもしれません? はじめての受診から療育まで』
著者:岡田俊
「発達が気になるけれど、どうすればいいかわからない」という親御さん向けに、受診・診断・療育の流れをマンガと文章でやさしく紹介。入門書としてわかりやすく、口コミでも高評価です。 Amazon 楽天
まとめ
自閉症スペクトラムは「育てにくい子」ではなく、「感じ方・考え方が違う子」。その特性を理解し、適切にサポートすることで、その子らしい生き方が実現します。書籍などを通じて学びを深めることが、支援や関係づくりの第一歩です。
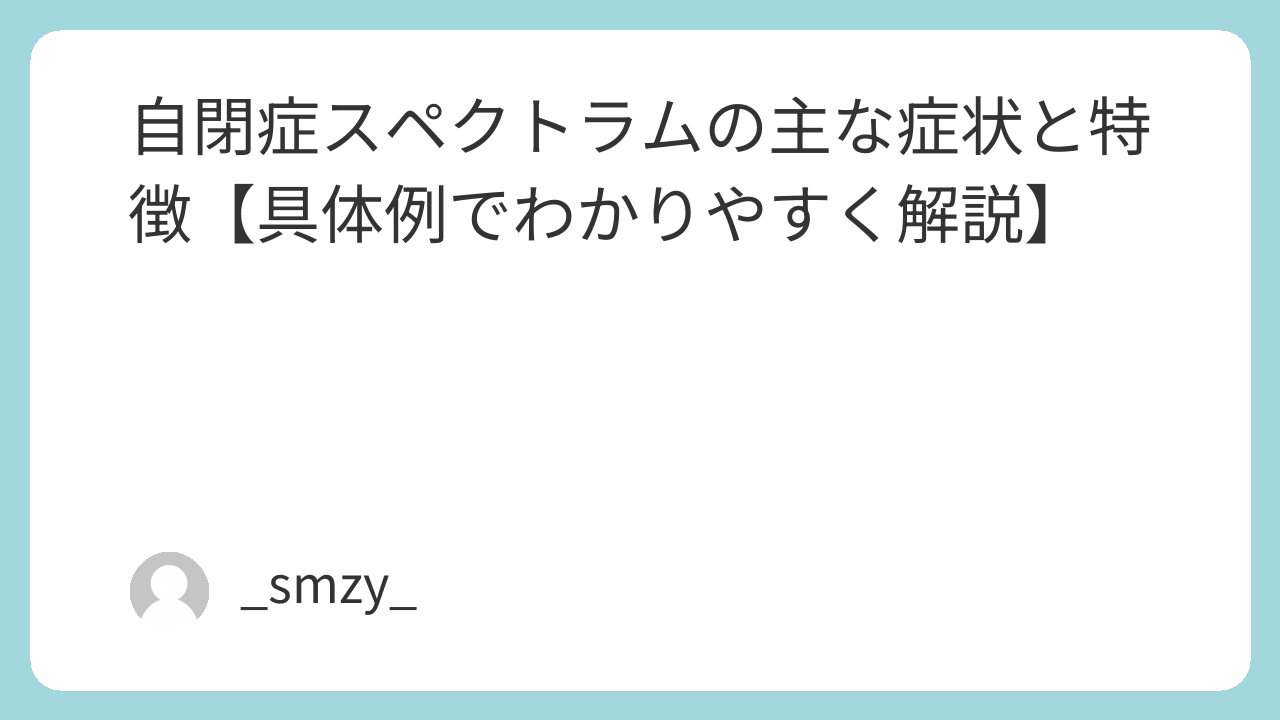
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ac02a39.0a3e2346.4ac02a3a.9c6d759c/?me_id=1213310&item_id=21143920&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1303%2F9784296201303_1_5.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ac02a39.0a3e2346.4ac02a3a.9c6d759c/?me_id=1213310&item_id=17800434&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4058%2F9784054064058.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ac02b33.d9696b73.4ac02b34.fede5924/?me_id=1278256&item_id=15934304&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F5360%2F2000004715360.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
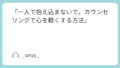
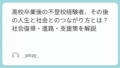
コメント