はじめに|“思春期後半”の不登校は深く、長引きやすい
中学2〜3年生になると思春期後半に入り、心と体は急成長します。
この時期の不登校は「学校が嫌」だけではなく、将来の不安や自己価値への葛藤など複雑な背景を伴うことが多いのです。
本記事では、中2・中3の不登校に特有の特徴と支援方法を、保護者・支援者向けにわかりやすく整理しました。
よくあるきっかけと心理状態
✅ 進路・受験へのプレッシャー
- 定期テスト・内申点・志望校への不安
- 頑張っても報われない無力感
- 自信喪失や無価値感 → 不登校につながるケースも
✅ 人間関係の疲労・孤立感
- 友人関係の固定化による居場所の喪失
- SNSでの無視・既読無視など“見えないいじめ”も影響
✅ 自分の将来・生き方への悩み
- “このままでいいのか”というアイデンティティの揺らぎ
- 学校という枠組みに疑問を感じ、登校を拒むケースも
不登校の典型的なサイン
- 授業への強い拒絶反応(特に受験科目)
- 「行きたいけど無理」が口癖に
- 睡眠リズムの乱れや昼夜逆転
- 家庭内での無気力や無関心が目立つ
- ゲームやネット依存の傾向が強まる
保護者としての具体的支援方法
❌ NG対応
- 「受験があるのに!」と責める言葉
- 「このままじゃ高校行けないよ」と脅す発言
- 「怠けてるだけ」と決めつける対応
✅ 支援のヒント
1. 「進路」より「今の気持ち」を聞く
まずは「何がつらいの?」と共感する姿勢を大切に。
2. 小さな目標で自信を取り戻す
「午後に制服を着てみる」「宿題を1問だけやってみる」など、できる範囲でOK。
3. 学校以外の選択肢を提示する
通信制高校、フリースクール、技能連携校など、別の道を一緒に調べてみると視野が広がります。
おすすめ書籍3選

思春期のつまずきを理解する理論書
不登校に陥る子どもたち: 思春期のつまずきから抜け出すプロセス

元中学生の心の声を描いた物語

不登校・発達特性への寄り添い方ガイド
子どもの心にどう寄り添う 不登校・思春期・発達障害との向き合い方 ※リンク Amazon 楽天
・不登校に陥る子どもたち: 思春期のつまずきから抜け出すためのプロセス
不登校の心理・発症メカニズムを整理した理論書。支援の方向性を学べます。
- 学校に行かない僕の学校
寮付きフリースクールを舞台にした体験小説。中学生本人の視点が心に響きます - 子どもの心にどう寄り添う 不登校・思春期・発達障害との向き合い方
思春期・発達特性・不登校に悩む家庭への具体的な関わり方を丁寧に指南してくれるガイド書
学校・支援機関との連携が重要
- 担任や学年主任との定期面談
- スクールカウンセラーへの家庭状況共有
- 教育相談センターやフリースクールなどの社会的資源を活用
- 作業療法士・心理士・児童精神科など専門家への相談を検討
家庭だけで抱え込まず、「この子に合う道」を一緒に考えてくれる大人を増やすことが大切です。
まとめ|不登校は“人生の失敗”ではない
中2・中3の不登校は、子どもが真剣に自分の生き方や将来と向き合っている証です。
家庭が「心の安全基地」となり、安心と共感を提供することで、子どもは再び社会とつながる力を取り戻していきます。
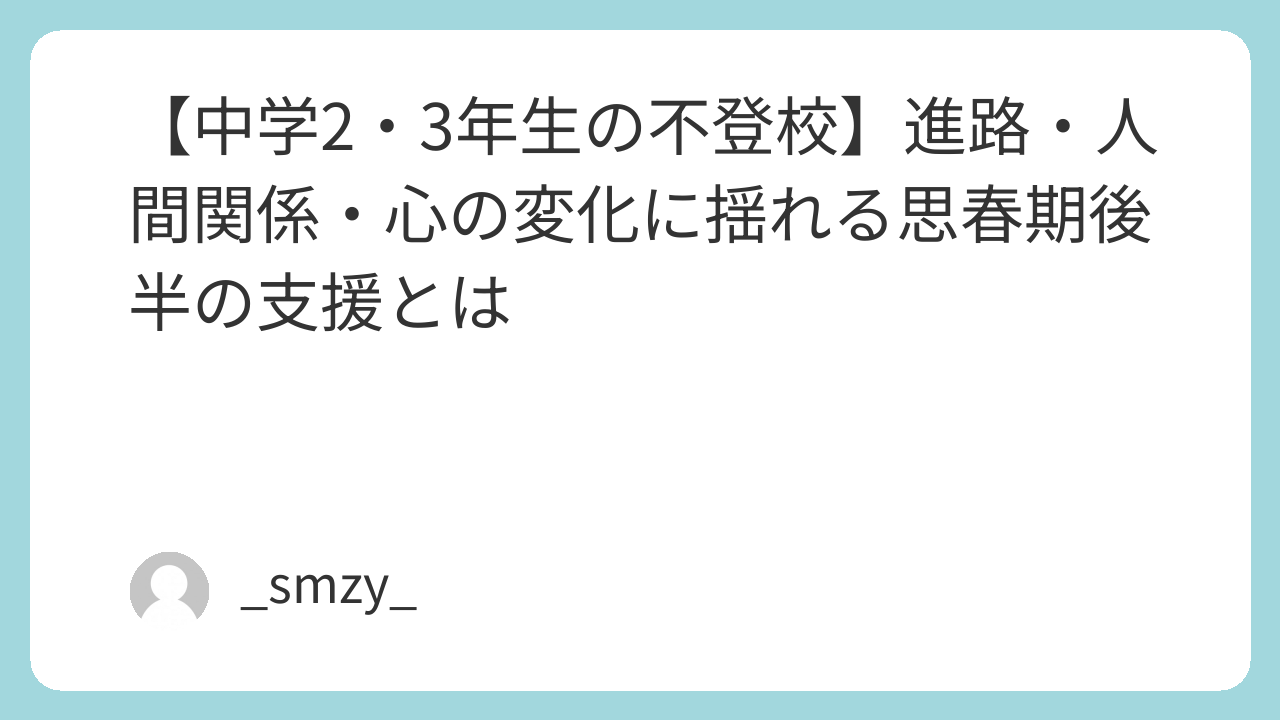
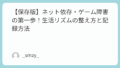
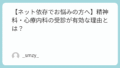
コメント