はじめに|「大人になる前に」訪れる心のつまずき
高校生は思春期の終盤に差し掛かり、自我や人生観が一気に発達する時期です。
同時に、「自分は何者か」「将来どうするのか」という大きな問いに向き合う必要もあります。
この時期に生じる不登校は、本人の価値観や進路の悩み、自立への不安、人間関係のストレスなどが重なり合い、複雑化・長期化しやすいのが特徴です。
高校生の不登校が生まれる主な背景とは?
✅ 進学・就職への強いプレッシャー
- 大学受験・専門進学・就職の選択に迫られる
- 将来に対して「希望が持てない」「選べない」不安
- 「親の期待」と「自分の本音」とのズレ
✅ 高校独特の人間関係の難しさ
- 自由度が高くなる分、距離感や空気を読む力が必要に
- クラス替えや部活動で孤立感が強まることも
- SNSを介した関係トラブル(既読スルー・仲間外れ)
✅ 自己肯定感の低下と孤立
- 「頑張れない自分」を責める
- 比較や評価が強くなり「どうせ無理」とあきらめに変わる
- 親や教師にも相談できず、ひとりで抱え込みがち
不登校につながりやすいサイン
- 授業・通学への無気力(遅刻や早退が増える)
- 定期テストや課題への極端なプレッシャー
- SNSやネットゲームへの過剰な没入
- 家族との会話の減少・反応の変化
- 睡眠障害や食欲の低下、体調不良の訴えが増える
保護者ができる対応|「なぜ行かないのか」より「何に困っているのか」を聞く
❌避けたい対応
- 「高校は自己責任でしょ」と突き放す
- 「将来どうするの?」とプレッシャーをかける
- 「せっかく入った高校なんだから続けなさい」と決めつける
✅支援のポイント
1. “将来”より“今の感情”に寄り添う
→ 「何がしんどい?」「どんなことが不安?」と感情を受け止める姿勢が大切。
2. 一度立ち止まることを肯定する
→ 「休んでも大丈夫」「回復する時間も必要」と、自分のペースを取り戻す支援を。
3. 学校以外の進路も視野に
→ 通信制高校・定時制・サポート校・高卒認定試験など、柔軟な選択肢があることを伝える。
専門機関や社会資源の活用も重要
- 担任・進路指導・スクールカウンセラーとの連携
- 地域のフリースクールやNPO支援団体の利用
- 心療内科・精神科・思春期外来への相談
- 作業療法士・臨床心理士による個別支援
🌱 高校生の不登校は、「社会とつながる感覚」を取り戻すことが支援の核となります。
📚 高校生の不登校を支える理解と支援のためのおすすめ書籍 3選
高校生の不登校には、進路や人間関係、心理的な葛藤など多くの背景があり、家庭や支援者の視野を広げる知見が求められます。以下の書籍は、いずれも実際の声や支援実践に基づく内容で、高校生の不登校理解に非常に役立ちます。
① 『学校に行きたくない君へ』
編集:全国不登校新聞社/ポプラ社 発行📖書籍紹介
この本は、実際に不登校を経験した若者たちの声をもとに作られた1冊です。
一方的な説教や励ましではなく、「そのままでいい」「あなたのままで大丈夫」といった言葉が届く構成になっており、読者が安心してページをめくれるよう工夫されています。
さまざまな年齢・背景を持つ当事者のインタビューが掲載されているため、高校生だけでなく、保護者や支援者の視点からも深い気づきが得られます。
📌記事との関連性
「自分だけが取り残されている」と感じやすい高校生にとって、同じように悩んだ人の言葉に触れることは大きな安心になります。
不登校の“孤独”や“将来への不安”に寄り添う内容は、記事内で触れた「共感的な支援」の実例として最適です。
🔗 楽天ブックスで見る & Amazonで見る
② 『私たちも不登校だった』
著:江川紹子/文藝春秋
🔗 楽天ブックスで見る & Amazonで見る
📖書籍紹介
本書は、様々な有名人・文化人たちが語る「不登校だった過去」についてまとめた対話・エッセイ集です。
どのエピソードもリアルで、決して順調な道のりではなかったからこそ、現在に至るまでの過程に説得力があります。
「不登校=失敗」ではなく、その後の人生の歩みがそれぞれにあるというメッセージが込められています。
📌記事との関連性
進学や就職を目前に控える高校生にとって、「不登校だった自分に未来はあるのか」という不安は非常に大きなものです。
この本に登場する人々のエピソードは、その不安に対し「大丈夫、道はひとつではない」と優しく伝えてくれます。
記事の「進路への不安と自己肯定感の低下」に具体的な補足として有効です。
③ 『誰にも頼れない 不登校の子の親のための本』
著:野々はなこ/あさ出版
🔗 楽天ブックスで見る & Amazonで見る
📖書籍紹介
この本は、自身の子どもが不登校になった著者が、親としての戸惑いや葛藤を正直に綴りつつ、どう乗り越えてきたかを丁寧に伝えてくれます。
専門用語や理論だけでなく、日々の声かけや見守り方など、親にとって実践的なヒントが数多く詰まっています。
「親がつらいとき、どうすればいいか」への答えも含まれており、心の支えになる一冊です。
📌記事との関連性
高校生の不登校では、親との距離感や信頼関係の揺らぎが大きく影響します。
この本の内容は、記事中で紹介した「家庭での関わり方」や「共感的な見守り」に通じており、保護者向けの補助教材として非常に有効です。
まとめ|「進学できるか」より「安心して生きていけるか」
高校生の不登校は、大人になる一歩手前の自立のプロセスの中で、悩みや葛藤が噴き出した結果でもあります。
「どうすれば前に進めるか」よりも、まずは「ここで休んでいい」と伝えること。
家庭がその心のセーフティネットになることで、子どもは自分なりのペースで再び歩き出す力を育てていけます。
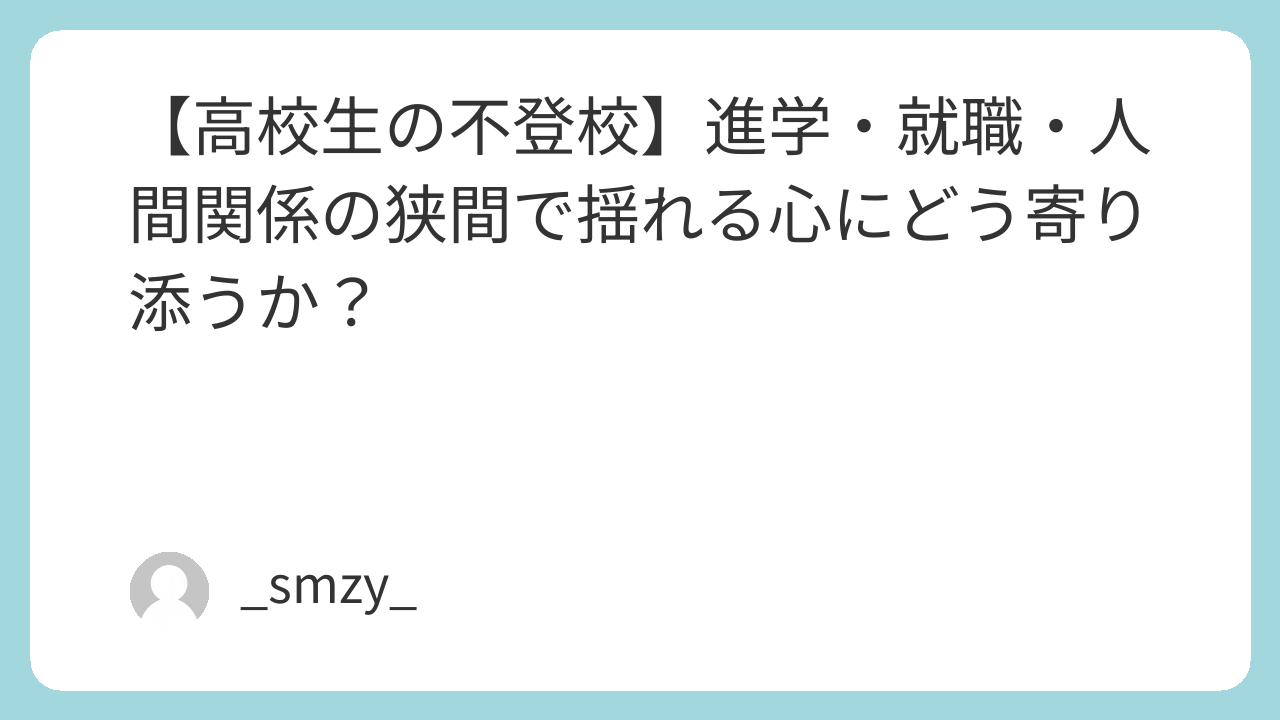
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ac02a39.0a3e2346.4ac02a3a.9c6d759c/?me_id=1213310&item_id=19222985&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9668%2F9784591159668.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ac02b33.d9696b73.4ac02b34.fede5924/?me_id=1278256&item_id=16362303&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F1982%2F2000000161982.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ac02a39.0a3e2346.4ac02a3a.9c6d759c/?me_id=1213310&item_id=21480412&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7330%2F9784866677330_1_6.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
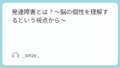
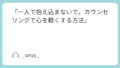
コメント