不登校の子どもに対する支援を考えるうえで最も重要なのは、「本人が何に困っているのか」という視点です。多くの場合、周囲の大人が「勉強についていけないのでは」「学校が怖いのでは」と予測して支援を始めますが、子ども本人の主観とはズレていることが少なくありません。主観的な困り感を丁寧に理解することで、より適切で効果的な支援につながります。
主観的な困り感とは?
「主観的な困り感」とは、本人が日常生活や学校生活において「つらい」「不安」「困っている」と感じていることです。それが明確な言葉になっていない場合も多く、表情・態度・沈黙のなかに表れていることもあります。
なぜ主観的な困り感の把握が重要なのか
- 支援のズレを防ぐ
大人が「正しい」と思っている支援が、子どもにとっては負担になることがあります。本人の気持ちをベースにすることで、無理のないサポートができます。 - 自己理解・自己肯定感の促進
「自分の気持ちを理解してくれる人がいる」と感じることは、子ども自身が自分を受け入れ、前を向くきっかけになります。 - コミュニケーションのきっかけになる
困り感についての対話は、子どもとの信頼関係を築くスタートラインでもあります。
主観的な困り感を把握するために必要なこと
1. 聴く姿勢を整える
子どもが話したくなるような、安心できる雰囲気をつくることが何よりも大切です。否定せず、急かさず、「聴いてくれる人がいる」という感覚を育てましょう。
2. 直接言語化できない場合の工夫
「絵を描いてもらう」「チェックリストを使う」「他の子の話を聞いたうえで自分に当てはまるかどうかを考えてもらう」など、間接的な方法も有効です。
3. 日常の観察と記録
行動パターンや表情、つぶやきなどから、言葉にならない困り感を読み取る努力も重要です。
4. 第三者のサポートを活用する
家族以外の信頼できる大人(スクールカウンセラー、フリースクールのスタッフなど)との対話を通して、本人が気づいていなかった困り感が見えてくることもあります。
主観的な困り感の理解に役立つ書籍3選
以下に紹介する書籍は、不登校の子どもが感じている「主観的な困り感」に寄り添い、理解を深める助けとなる実在の書籍です。
① 『学校に行かなかった僕が、あのころの自分に今なら言えること』
不登校の当事者でありジャーナリストでもある著者が、自身の体験と400人以上への取材をもとに、「しんどかったあの時期の自分」に語りかけるように綴った60の言葉。本人の目線から主観的な困り感を知ることができる貴重な一冊です。 👉Amazonでみる 👉楽天で見る
② 『全国フリースクールガイド 2025‑2026年版 小中高・不登校生の居場所探し』
全国540か所以上のフリースクールや支援機関を掲載したガイドブック。「学校に居場所がない」と感じる子どもたちの困り感に対して、実際に足を運べる選択肢を提供してくれます。親子で読んで、話し合うきっかけにもおすすめです。 👉Amazonでみる 👉楽天で見る
③ 『学校に行きたくない君へ』
不登校の当事者による体験談を中心とした構成で、共感を通して「自分の困り感」に気づくきっかけとなる一冊。子ども本人が「こんなふうに感じているのは自分だけじゃない」と思える安心感が得られます。 👉Amazonでみる 👉楽天で見る
まとめ
不登校の子どもが抱える困り感は、多くの場合、言葉にならない「主観的なつらさ」として存在しています。まずはその気持ちを受け止め、理解しようとする姿勢こそが、支援の第一歩です。
紹介した3冊の書籍は、それぞれの立場から不登校の子どもたちの気持ちに寄り添い、支援するためのヒントを与えてくれます。ぜひ一度手に取ってみてください。
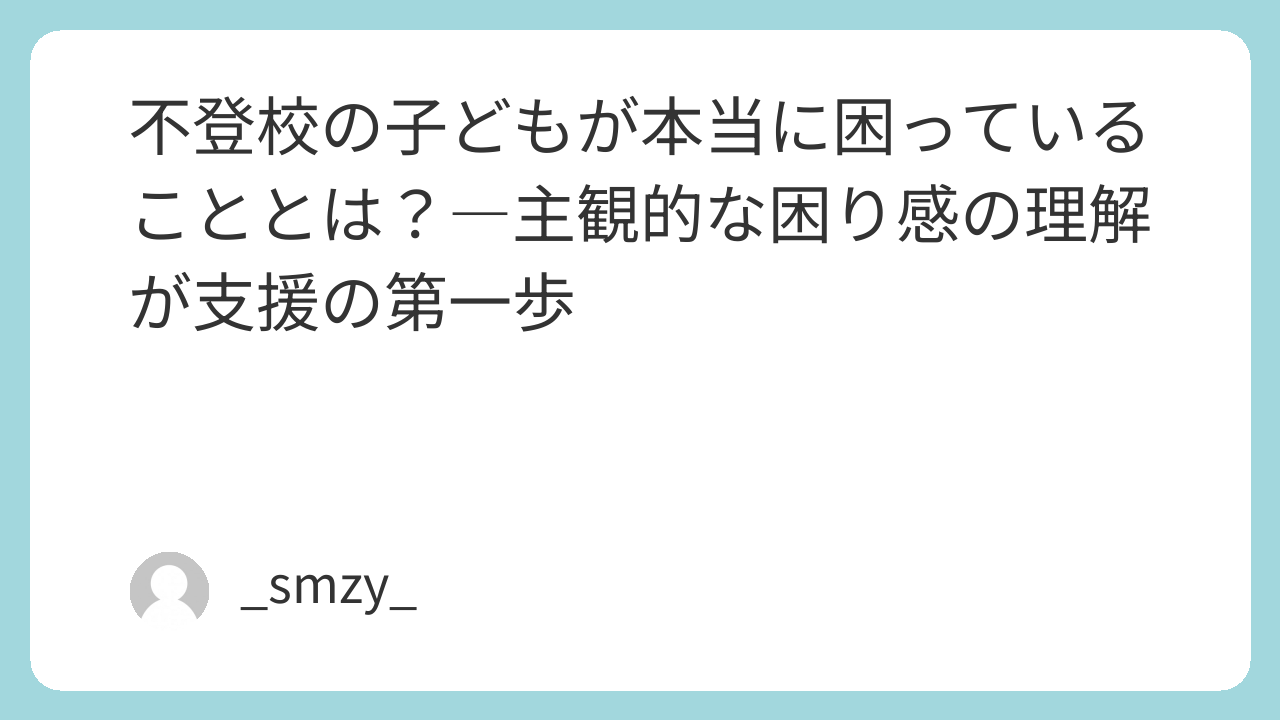
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ac02a39.0a3e2346.4ac02a3a.9c6d759c/?me_id=1213310&item_id=21596531&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6207%2F9784479786207.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ac02a39.0a3e2346.4ac02a3a.9c6d759c/?me_id=1213310&item_id=21546961&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5787%2F9784908555787_1_6.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ac02a39.0a3e2346.4ac02a3a.9c6d759c/?me_id=1213310&item_id=19222985&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9668%2F9784591159668.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
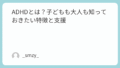
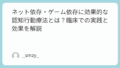
コメント