自己効力感とは?
「自己効力感(self-efficacy)」とは、心理学者バンデューラによって提唱された概念で、「自分にはこの課題を乗り越える力がある」と信じる感覚を指します。
自己効力感が高い人は、困難に直面しても「なんとかなる」と考え、粘り強く取り組みます。
一方で、自己効力感が低い人は、「どうせできない」「やっても無駄だ」と感じやすく、行動を起こす前に諦めてしまうことが多くなります。
自己効力感と依存症の関係
依存症の背景には、ストレス対処の難しさや自己肯定感の低さ、感情調整の困難さがありますが、それらと深く関連しているのが自己効力感です。
たとえばアルコールやネット依存の人は、問題に直面したとき「他の方法では対処できない」と感じており、「自分の力で状況を変えられない」=自己効力感の低さが根底にあることが少なくありません。
特に、**小児期逆境体験(ACEs)**を経験した人は、幼少期から自分の行動が状況を変える経験をしにくく、成長してからも無力感を抱きやすくなります。
自己効力感と不登校の関係
不登校の子どもたちもまた、**「学校でうまくやっていける気がしない」「どうせ怒られる」「行ってもいいことがない」**という思いを抱えています。
これは、学校生活で成功体験が積み重ならず、自己効力感が育っていないことが原因となっている場合があります。
たとえば勉強でつまずいた、友人関係でトラブルがあったなどの経験が続くと、「どうせまた失敗する」と思い、登校への意欲が失われていきます。
自己効力感を高める支援とは?
自己効力感は、成功体験・代理体験・言語的説得・生理的状態の4つの要素によって高めることができます。
1. 成功体験
小さな「できた!」を積み重ねることが最も重要です。例えそれが「朝起きて顔を洗えた」「宿題の1ページだけやった」などであっても構いません。
2. 代理体験
似た立場の他者が成功している様子を見ることで、「自分にもできるかも」という気持ちが芽生えます。不登校や依存症から回復した当事者の体験談は効果的です。
3. 言語的説得
信頼できる人からの「あなたならできるよ」「がんばってるね」といった声かけも、自己効力感を支える要素になります。
4. 生理的状態の調整
不安や疲労が強いと、「できるはず」と思えません。生活リズムを整えることも土台になります。
おすすめの書籍紹介
以下の本は、自己効力感・依存症・不登校・発達障害に関係する内容が学べる実用的な書籍です。支援者だけでなく、本人や保護者の方にもおすすめです。
◆ レジリエンスが身につく 自己効力感の教科書
逆境を経験した人が回復する鍵となる「レジリエンス」と「自己効力感」の関係に注目した一冊です。依存症に悩む方の多くは、自分には困難を乗り越える力がないという“無力感”を抱えています。本書では、日常の小さな行動から自信を取り戻し、自らの手で変化を起こす方法が丁寧に紹介されています。
ブログ記事で触れたACEs(逆境的小児期体験)との関係でも、自己効力感の向上が依存症からの回復の土台になることを改めて感じさせてくれます。
◆ 発達障害の子の自己肯定感をはぐくむ本
発達障害のある子どもたちは、小さな失敗体験の積み重ねから「自分はダメなんだ」と感じやすく、自己肯定感が下がる傾向があります。本書は、特性に応じた声かけや環境調整によって、自信を育てていくための具体的な関わり方を提案しています。
依存症に関連する背景として発達障害があるケースも少なくありません。家庭や支援の場面で、肯定的な関わりを通じて「自己効力感」を回復するヒントが詰まった一冊です。ブログで紹介した支援的アプローチとの親和性も高い内容です。
◆ アディクション・サイコロジー ─ 脱依存への支援
依存症の心理的メカニズムから、支援に必要な視点までを体系的に解説した専門的な書籍です。ACEsやトラウマの影響に触れながら、依存が「感情をコントロールするための手段」として機能していることに焦点を当てています。
このブログで取り上げた「依存症と自己効力感の関係」や「ACEsとのリンク」を深く理解するための理論的な裏付けとして、非常に有用な内容です。現場の支援者だけでなく、当事者や家族にも一読をおすすめしたい一冊です。
まとめ
自己効力感は、「自分で自分の人生を動かせる」という感覚であり、依存症や不登校の予防・回復に不可欠な心理的資源です。
支援する側としては、「やらせる」のではなく「できたと実感できる環境づくり」がカギになります。
小さな成功を一緒に喜びながら、少しずつ「自分にはできる」と思える体験を重ねていきましょう。
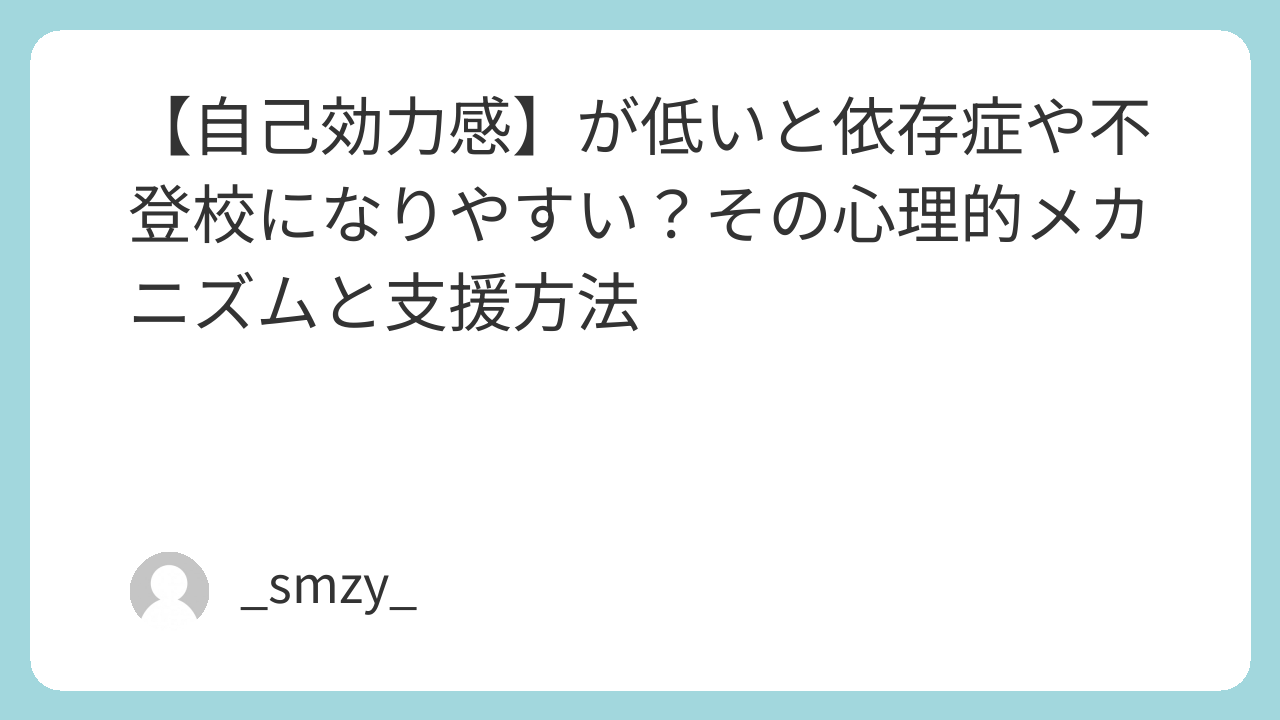
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ac02a39.0a3e2346.4ac02a3a.9c6d759c/?me_id=1213310&item_id=21329389&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9629%2F9784862809629_1_3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ac02a39.0a3e2346.4ac02a3a.9c6d759c/?me_id=1213310&item_id=20392496&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3743%2F9784804763743_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ac02a39.0a3e2346.4ac02a3a.9c6d759c/?me_id=1213310&item_id=20885352&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0239%2F9784414300239_1_3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
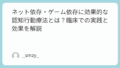
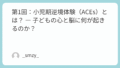
コメント