はじめに
不登校という言葉を聞くと、「怠けているのでは?」「行こうと思えば行けるのでは?」と考えてしまう人もいるかもしれません。
しかし、**小児期逆境体験(Adverse Childhood Experiences:ACEs)**がある子どもにとって、不登校は“行かない”選択ではなく、“行けない”状態であることがあります。
本記事では、ACEsと不登校の関係について、学校・家庭・支援者の視点から解説します。
1. ACEsとは? 不登校との関係
ACEsは、子ども時代に経験するつらい出来事や環境を指します。代表的なものには以下があります。
- 身体的・心理的虐待
- ネグレクト(育児放棄)
- DVの目撃
- 親の精神疾患やアルコール依存
- 離婚や死別など家庭の大きな変化
これらの体験は、子どもの脳や神経系の発達に影響し、ストレスに対して過敏になることがあります。その結果、学校のような刺激が多く、対人関係が密な場は、本人にとって大きな負担になり得ます。
2. 学校が「安心の場」でないとき、どうなるか
学校は本来、子どもが学び、成長するための安全な場所です。
しかし、ACEsがある子どもは、以下のような理由で学校を安心と感じられないことがあります。
- クラスや教室が常に騒がしく、落ち着けない
- 教師や同級生との関係が緊張状態になりやすい
- 評価や叱責に対して過剰に恐怖や不安を感じる
- 身体症状(頭痛、腹痛、倦怠感)が強く出やすい
このような状態では、毎朝「学校に行く」という行為が大きな精神的ハードルになります。
3. 「行けない」と「行かない」の違い
保護者や周囲の大人から見ると、子どもがゲームやスマホをしている姿は「行こうと思えば行けるのでは」と見えるかもしれません。
しかし、ACEsが関わる場合、学校は強いストレス源になっており、体や脳が“行く”ことを拒否している状態です。
- 行けないケース:体調不良や強い不安、過去のトラウマを思い出す恐怖
- 行かないケース:学校に魅力を感じず、他の活動を優先している
ACEsによる不登校は、前者の「行けない」に該当することが多くあります。
4. 過去の体験が登校拒否に影響するケース
例えば以下のようなパターンがあります。
- 家庭での暴力経験があり、大声や怒鳴り声に過敏
- 過去にいじめを受け、再び同じことが起きるのではと恐れている
- 親の精神的な不安定さに日常的にさらされ、自己肯定感が低い
これらは、表面的には「ただの不登校」に見えても、背景には長期的な心理的ストレスが潜んでいる場合があります。
5. 支援の方向性 ― 環境調整と家庭の安心感
ACEsがある子どもの不登校支援は、単なる「登校刺激」だけでは不十分です。必要なのは環境調整と安心の回復です。
- 家庭での安心感の確立
- 責めず、まず受け止める
- 日常のルーチンを安定させる
- 学校での配慮
- 別室登校や時短登校の導入
- 担任以外の安全な関係の先生とつながる
- 多職種連携
- スクールカウンセラー、医療、福祉と連携
- 心理的ケアと生活支援の両立
まとめ
ACEsがある子どもの不登校は、「怠け」や「わがまま」ではなく、過去の体験と現在の環境が複雑に影響した結果です。
まずは安心できる場をつくり、子どもが「また行ってみようかな」と思えるようになるまでのプロセスを支えることが大切です。
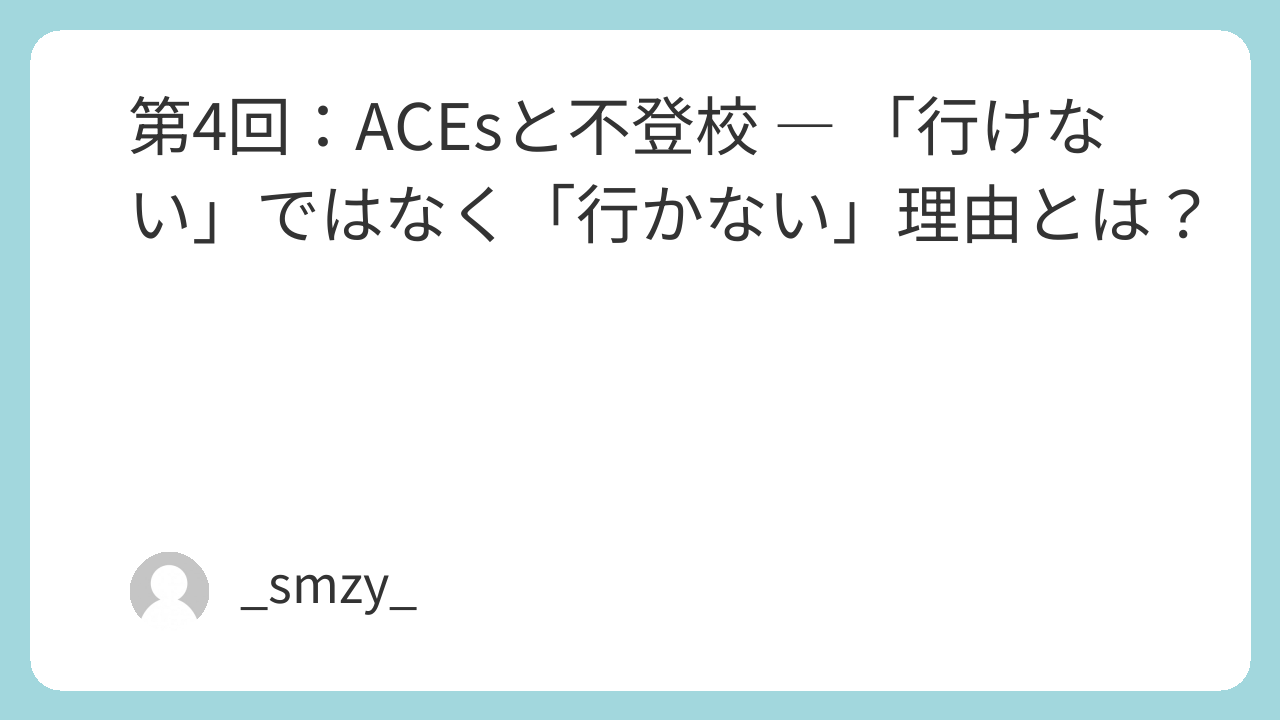
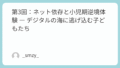
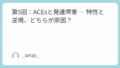
コメント