はじめに
子どもが示す行動や感情の困難の背景には、先天的な発達特性と後天的な環境要因の両方が関わることがあります。
なかでも、**小児期逆境体験(Adverse Childhood Experiences:ACEs)**は、発達障害に似た症状を引き起こすことがあり、現場での判断を難しくします。
たとえば、集中できない、衝動的、感情が爆発する、対人関係が苦手――これらはADHDやASDの特徴に見えますが、実は長期的な心理的ストレスやトラウマによる脳機能の変化でも起こります。
この記事では、発達障害とACEsの見分け方の難しさ、脳科学的背景、多職種連携の重要性について解説します。
1. 発達障害とACEs、それぞれの特徴
発達障害(例:ASD、ADHD、LDなど)
- 原因:主に先天的な脳の発達差
- 症状の安定性:年齢を通じて一貫した特徴が見られる(例:小さい頃からずっと集団が苦手)
- 特徴:
- ASD:社会的コミュニケーションの困難、こだわり、感覚過敏
- ADHD:注意の持続困難、衝動性、多動
- LD:特定の学習領域(読み・書き・計算)の困難
- 経過:環境調整で困難は軽減するが、特性そのものは持続
ACEs(小児期逆境体験)
- 原因:幼少期の慢性的ストレスやトラウマ体験
- 内容の例:
- 身体的・心理的虐待
- ネグレクト(育児放棄)
- DVの目撃
- 親の精神疾患や依存症
- 家庭の不安定さ(離婚、死別など)
- 症状の変動性:環境や安心感の有無によって症状が改善・悪化しやすい
- 影響の特徴:
- 扁桃体の過敏化(恐怖や不安が強まる)
- 前頭前野の抑制機能低下(感情コントロールが難しくなる)
- 記憶・注意機能の低下(授業に集中できない)
2. 重なる行動と見極めの難しさ
発達障害とACEsは、以下のように外から見ると似た行動が現れます。
| 見られる行動 | 発達障害による可能性 | ACEsによる可能性 |
|---|---|---|
| 授業中に立ち歩く、集中が続かない | ADHDの注意機能特性 | トラウマによる過覚醒、注意散漫 |
| 他者との距離感が極端 | ASDの社会的認知の特性 | 人間関係への警戒・不信感 |
| 怒りや癇癪が突然爆発 | 衝動性や感覚過敏 | ストレスによる過剰反応 |
| 学校への遅刻・欠席 | 睡眠リズム障害 | 不安や回避行動 |
3. 事例で見る混同の危険性
事例A
小学4年生の男児。授業中に立ち歩きや忘れ物が多く、ADHDを疑われた。
しかし面談で、家庭内での暴力目撃経験があり、夜眠れない・突然泣き出すなどの症状も確認。心理士の評価でPTSD傾向が判明。
➡ 発達障害単独ではなく、ACEsによる二次的な注意困難と判明。
事例B
中学1年生の女子。集団活動を極端に避け、対人交流が苦手。家庭環境は安定しており、幼少期から同様の傾向あり。
➡ ACEsの影響ではなく、ASDによる社会的認知の特性と診断。
4. 脳科学から見る違い
- 発達障害:脳の配線や機能の一部が先天的に異なっている。発達の過程全体に影響。
- ACEs:慢性的ストレスによりコルチゾールが過剰分泌され、扁桃体・前頭前野・海馬の機能が変化。安全な環境で徐々に回復する可能性あり。
5. 両方を持つ子どももいる
実際の臨床現場では、発達障害+ACEsというケースが少なくありません。
例えばADHDの衝動性を持つ子が、叱責やいじめを繰り返し経験し、それがトラウマとなって二次的な不安障害を発症することもあります。
この場合、「どちらを先に支援するか」ではなく、両方を同時に視野に入れる必要があります。
6. 多職種連携での見極め
誤診や支援の遅れを防ぐためには、以下のような連携が重要です。
- 医師:診断、薬物療法の適否判断
- 心理士:心理検査、トラウマ評価、カウンセリング
- 作業療法士(OT):感覚統合、生活リズム支援、安心感の回復
- 学校:日常行動の観察、学習面の調整
- 保護者:家庭での様子、過去の経験の共有
7. 支援の実際
- 発達特性に合わせた環境調整
- 視覚支援(スケジュール提示)
- 刺激を減らす(静かな学習環境)
- トラウマケア
- 安全な人間関係の確立
- 感情表現を促す活動(アート、遊び)
- 身体感覚の安定化
- 深呼吸、リズム運動、感覚統合遊び
- 保護者支援
- 過度な叱責を避ける
- 日常のルーチン化
おすすめ書籍 3選
1. 『発達障害・愛着障害・小児期逆境体験(ACE)のある親子支援ガイド』(高山恵子 著)
発達障害、愛着障害、ACEsを抱える親子への支援を、事例を交えて具体的に解説する日本語の実践ガイドです。子育て支援センターや学校、保健師、カウンセラーといった現場の支援者にとって、日常的に使える対応やアプローチ法が豊富にまとめられています。Amazon 楽天
2. 『小児期の逆境的体験と保護的体験』 ジェニファー・ヘイズ=グルード & アマンダ・シェフィールド・モリス 著(日本語訳)
ACEs(逆境体験)と対となる「保護的体験(PACEs)」という概念を提示し、子どものレジリエンス(回復力)の育成に焦点を当てた一冊。心理学会による最新研究をもとに、逆境と回復の両側を統合的に理解することに役立ちます Amazon 楽天
まとめ
発達障害とACEsは原因も経過も異なりますが、行動の見え方は非常に似ています。
一方的に「発達障害だ」「トラウマだ」と決めつけず、両方の視点を持って評価・支援することが、子どもと家族の安心につながります。
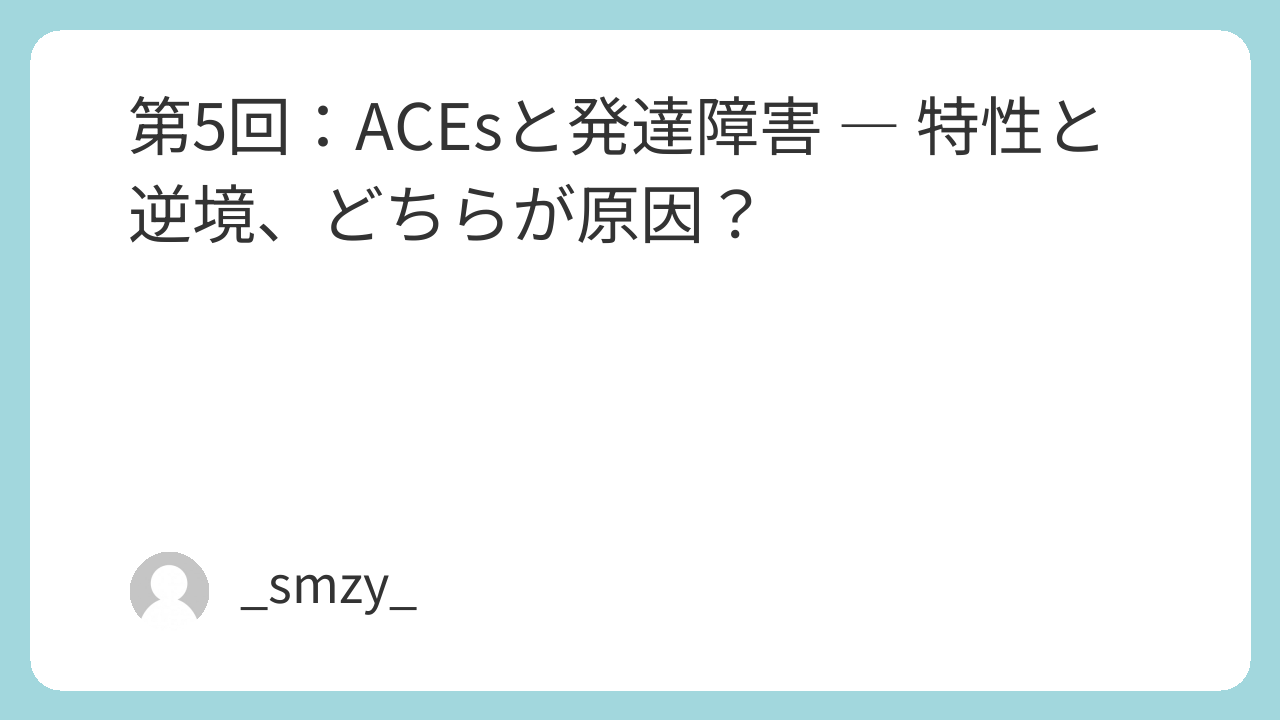


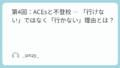
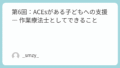
コメント