✅ この記事のポイント
- 「学校がこわい」「行くとお腹が痛くなる」など、心の不安が原因の不登校を解説
- 作業療法士の視点から、家庭での接し方・やってはいけない言動も紹介
- 不登校初期対応や支援先につなぐ判断基準もわかる
心理的・情緒的要因型の不登校とは?
このタイプの不登校は、子どもの心の中にある不安や恐怖、緊張感が原因となって、登校が困難になる状態です。
見た目には元気そうでも、学校に行こうとすると体に不調が出たり、泣いてしまったりするのが特徴です。
主な原因の一例
- クラスでの人間関係(いじめ・仲間外れ)
- 教師との相性や指導への恐怖感
- 発表・注目されることへの不安(社交不安)
- 勉強のつまずきによる劣等感
- 完璧主義や強い自己否定感
実際によく聞く子どもの声
- 「どうしても教室に入れない」
- 「誰かに見られている気がする」
- 「友達に嫌われてるかも」
- 「間違えたら笑われる気がする」
- 「なんか怖いけど、理由は自分でもわからない」
やってはいけない対応3選
①「行けば慣れるから」
→ 不安が強い子には逆効果です。無理に登校させようとすると、不登校が長期化することも。
②「気のせいでしょ」「そんなの考えすぎ」
→ 子どもは「わかってもらえない」と感じ、さらに閉じこもりがちになります。
③「他の子はちゃんと行ってるよ」
→ 他人との比較は、自己肯定感を下げるだけ。子どもにとっては追い打ちになります。
家庭でできる支援のヒント【作業療法士の視点から】
✔ 安心できる場所・時間をつくる
まずは、「学校に行く・行かない」ではなく、子どもが安心して過ごせることを最優先に。
- 自分の部屋でゆっくり過ごす
- 好きな音楽や動画で気持ちを落ち着ける
- 好きな遊びや創作活動に集中する(塗り絵・折り紙・ゲーム制作など)
✔ 「話す」より「聴く」ことに専念
- アドバイスより、ただ聴くだけで十分
- 返答に困ったときは「そっか」「そう感じたんだね」だけでも◎
- 子どもが言葉にできない気持ちは、絵や行動に出ることも(描画法や観察が有効)
✔ 日中の生活リズムを少しずつ整える
学校に行けなくても…
- 朝起きて着替える
- 朝ごはんを一緒に食べる
- 午前中にちょっと外に出る(ベランダ、庭、近所の散歩)
などの**「生活のリハビリ」**を意識。
相談や支援が必要なサインとは?
以下のような様子が見られたら、専門家への相談を検討しましょう。
- 1か月以上登校できない状態が続く
- 表情が乏しく、感情の起伏が少ない
- 睡眠や食事に著しい乱れがある
- 「死にたい」「消えたい」などの言葉が出てきた
- 自傷行為や暴言・暴力などが見られる
支援につながる機関・選択肢
- スクールカウンセラー
学校内で心理的サポートが受けられる - 教育支援センター・適応指導教室
学校に戻る前の練習として利用できる - 児童精神科・心療内科
不安障害・うつ・発達障害などが隠れている場合もあるため、医療的な判断が必要なことも - 作業療法士(OT)
生活・感情・行動の調整支援が得意な専門職です。発達支援や病院に配置されていることも
まとめ|不安の根本は「守られたい気持ち」
子どもが不登校になる背景には、自分ではどうにもできない不安があります。
それを「学校に行けない」という形で表現しているだけです。
無理に引っ張るより、「ここにいていいんだよ」と安心を伝えることが第一歩です。
不登校は「成長を止めた」のではなく、「回り道の中でも育っている」時間なのです。
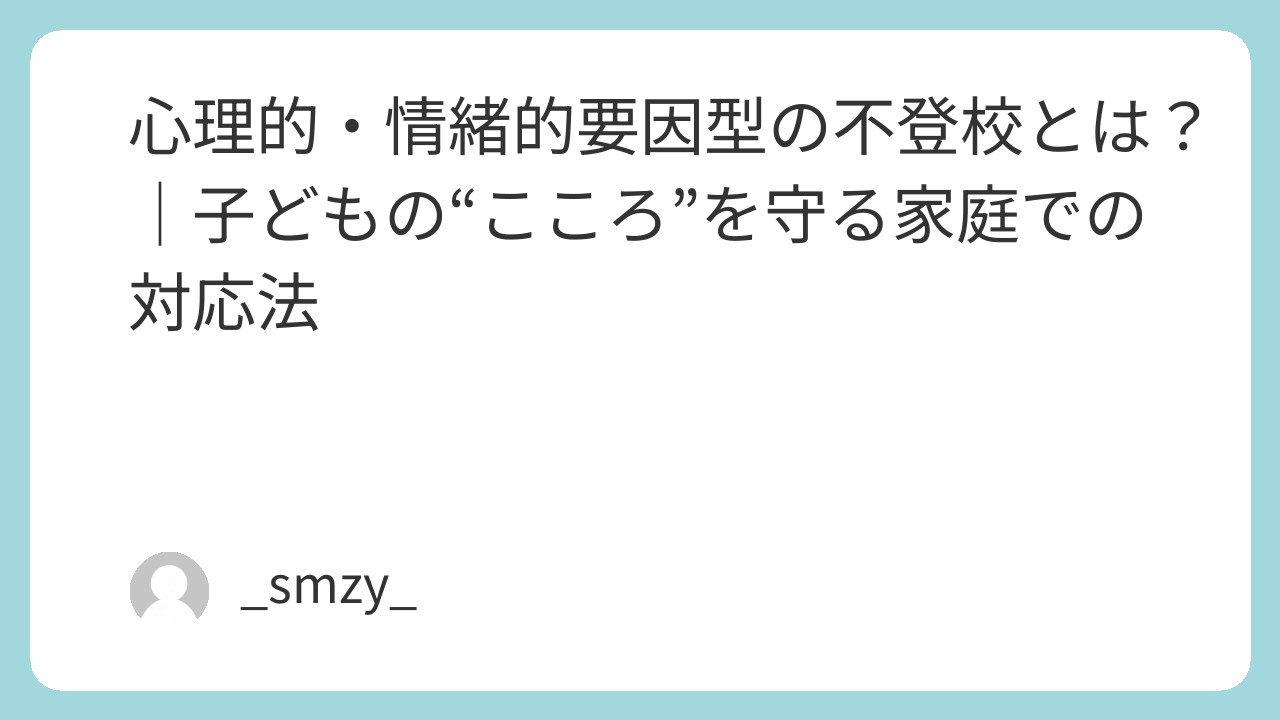
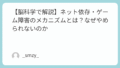
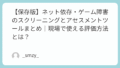
コメント