はじめに
不登校の背景には、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。前回は「身体的要因」について解説しましたが、今回は「環境的要因」に焦点を当てます。
家庭環境、学校環境、そして社会環境が、子どもの心理や行動にどのような影響を与えるのかを一緒に考えていきましょう。
環境的要因とは?
環境的要因とは、子どもを取り巻く外的な環境によって生じる不登校の原因です。以下のような3つの主な領域に分けられます。
1. 家庭環境
- 両親の不仲や離婚
- 経済的困窮
- 過保護・過干渉
- 子どもへの無関心や虐待
- 兄弟姉妹との比較やトラブル
家庭は、子どもが安心して帰れる場所であるべきですが、居心地が悪かったり心理的なストレスを感じると、学校に行くエネルギーが奪われてしまうことがあります。
2. 学校環境
- いじめや仲間外れ
- 教師との関係不全
- 学業への不安やプレッシャー
- 校則・指導の厳しさ
- クラスの雰囲気が合わない
学校は学ぶ場であると同時に、人間関係を育む場でもあります。そこでの不適応は、不登校の直接的な引き金になりやすいです。
3. 社会環境
- 地域の孤立
- ネット・SNSでのトラブル
- コロナ禍による生活の変化
- 働き方の変化による親子関係の希薄化
現代社会では、インターネット環境や家庭外での出来事が子どもの心理に大きく影響します。特にSNSでの誹謗中傷や炎上などは、深刻な問題となり得ます。
環境的要因にどう向き合うか?
家庭の役割を見直す
家族の中でのコミュニケーションを見直すことが大切です。子どもが「受け入れられている」「話を聴いてもらえる」と感じる時間を日常的に作ることが、安心感につながります。
学校と連携する
担任教師やスクールカウンセラー、場合によっては教育委員会との連携も必要です。学校側も個別対応を進める必要があります。
社会的資源を活用する
子ども家庭支援センター、NPO、フリースクールなど、社会的な支援を活用することが、家族の負担を減らし、子どもの自立を助けることにつながります。
おわりに
環境的要因は、家庭や学校、社会全体が関わる複雑な課題です。しかし、1つずつ課題に気づき、少しずつ関係性を築き直していくことが、不登校支援の第一歩です。
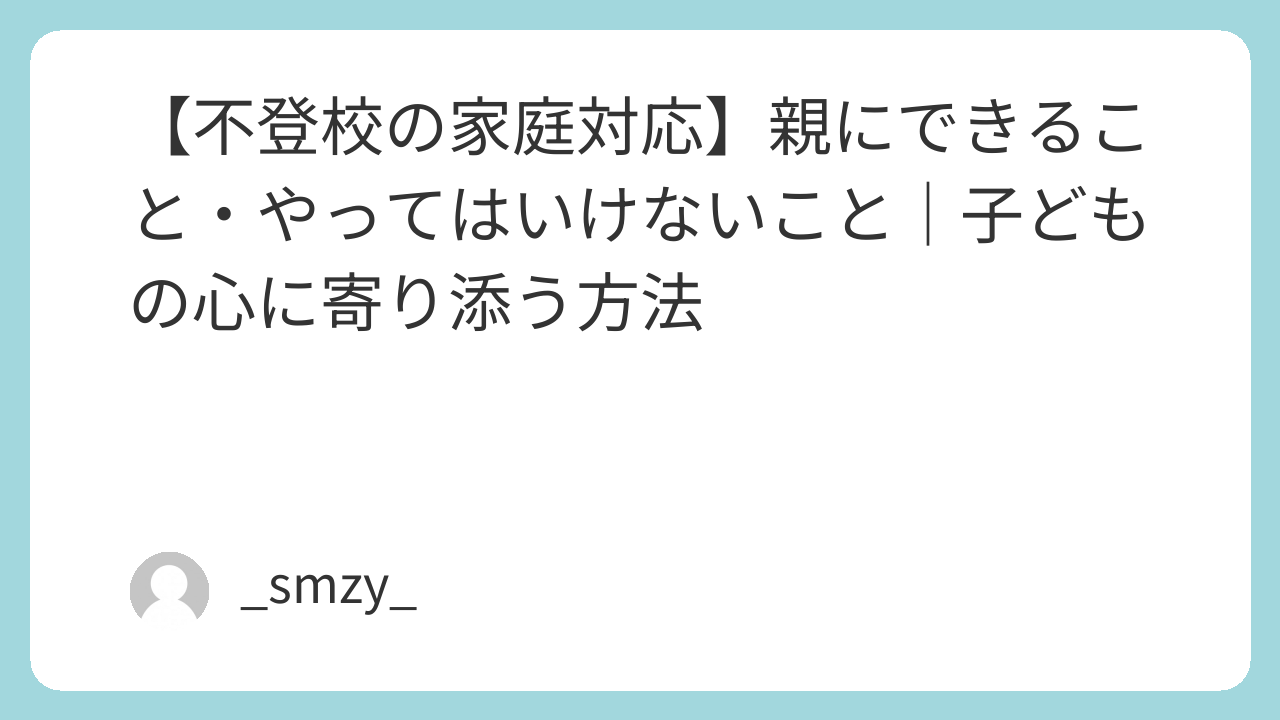
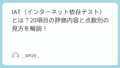
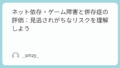
コメント