ネット依存やゲーム障害は単独で存在することは少なく、しばしばうつ病、不安障害、ADHDなどの精神疾患や、睡眠障害、視力障害などの身体的問題と併存しています。本記事では、それら「併存症」の評価について、臨床現場の視点から詳しく解説します。
【併存症とは?】
併存症とは、ネット依存・ゲーム障害と同時に存在する別の疾患や障害のことを指します。特に思春期〜青年期においては、以下のような疾患との併存が多く見られます。
- うつ病・抑うつ状態
- 不安障害(社交不安・パニック障害など)
- 注意欠陥・多動性障害(ADHD)
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 強迫性障害(OCD)
- 睡眠障害(不眠・昼夜逆転)
- 身体的問題(視力低下、姿勢異常、頭痛など)
【評価が重要な理由】
ネット依存やゲーム障害の背後に併存症がある場合、単純な制限や指導だけでは改善が見込めません。根本的な治療や支援を行うためには、背景にある疾患を正確にアセスメントすることが不可欠です。
【代表的な評価ツールと方法】
1. 精神症状の評価ツール
- PHQ-9:うつ症状をスクリーニング
- GAD-7:不安症状のスクリーニング
- CAARS:ADHD傾向の把握
- AQ:ASD傾向の簡易評価
2. 睡眠・身体症状の評価
- PSQI(ピッツバーグ睡眠質問票): 睡眠の質と問題点の可視化
- 身体症状チェックリスト: 頭痛、倦怠感、視力、姿勢などの身体的症状をスクリーニング
3. 保護者・学校からの聞き取り
行動観察や保護者・教師からの情報も極めて重要です。特にADHDやASDの特性は、本人の主観より周囲の観察が有効です。
【作業療法士の役割】
精神科作業療法士は、ネット依存やゲーム障害の影に潜む併存症を評価し、日常生活や社会適応への支援計画を立てる重要な役割を担っています。生活リズムの回復や対人関係スキルの向上など、作業療法的アプローチが効果を発揮します。
【まとめ】
ネット依存やゲーム障害は、見えている問題の「表層」に過ぎません。真の支援には、うつ、不安、発達特性、身体的問題といった「併存症」の正確な評価と理解が欠かせません。適切なスクリーニングとアセスメントを行い、個別に合わせた支援を行いましょう。
おすすめ記事:
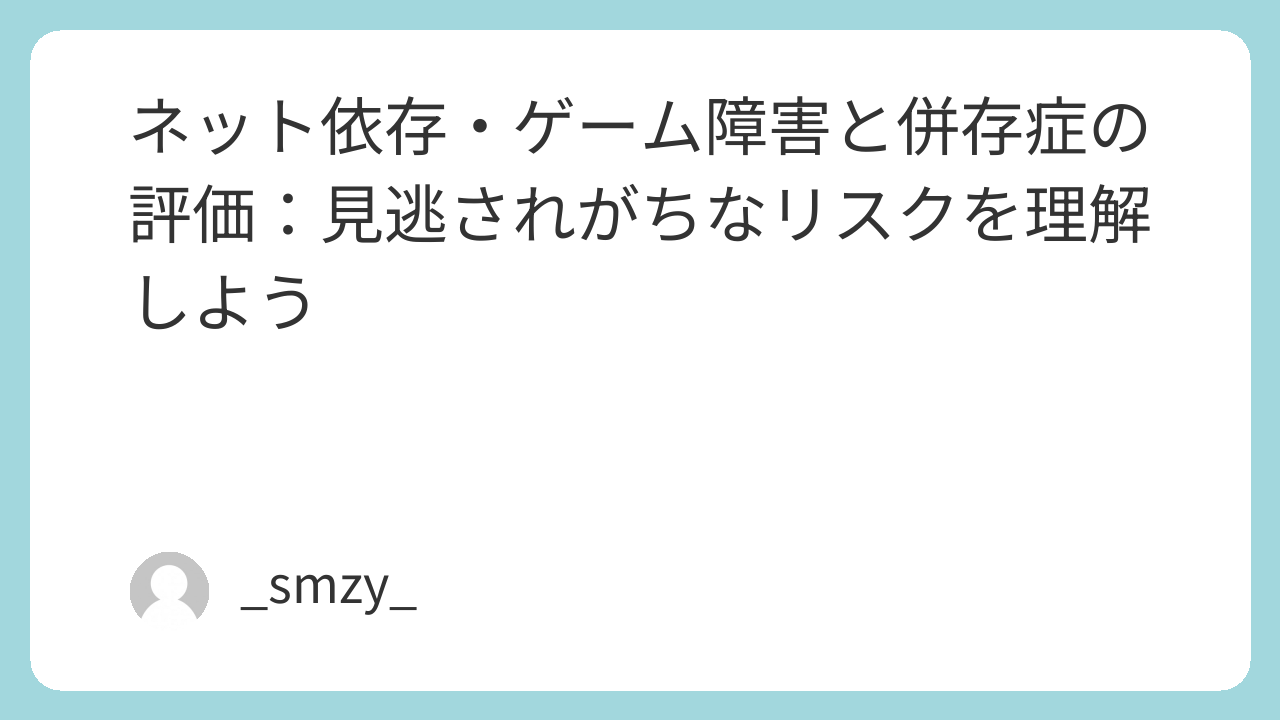
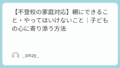
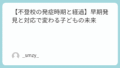
コメント