ADHDとは?脳の特性と向き合うために知っておきたいこと
ADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder:注意欠如・多動症)は、発達障害の一種で、「集中できない」「じっとしていられない」「つい衝動的に動いてしまう」といった行動が日常生活に影響を与える状態を指します。
これは性格の問題ではなく、脳の働き方の特性に関わるものです。
ADHDの主な3つの特性
1. 不注意(集中が続かない)
- 忘れ物が多い
- 話を聞いても気が散る
- 細かい作業が苦手
2. 多動性(じっとしていられない)
- 常に動いている
- 授業中に席を立つ
- おしゃべりが止まらない
3. 衝動性(考える前に行動)
- すぐに口をはさんでしまう
- 順番が待てない
- 思いつきで行動して後悔する
ADHDの原因と診断
ADHDの主な原因は、脳内の神経伝達物質(ドーパミンやノルアドレナリン)の働きの違いと考えられています。遺伝的要因も関係するとされ、家族にADHD傾向のある人がいるケースも多いです。
診断は小児科や精神科などで行われ、問診・行動観察・心理検査などを通じて総合的に判断されます。
ADHDのある人の強みと可能性
ADHDのある人には、以下のようなポジティブな特性も多く見られます:
- 発想力・創造力が豊か
- 一つのことに没頭できる「過集中」
- 直感力が鋭い
- 明るくエネルギッシュ
支援や工夫によって、自分の強みを社会で活かすことができます。
ADHDと共に生きるための支援方法
- タイマーやチェックリストでスケジュールを「見える化」
- 静かな環境で集中できる工夫
- 支援者が「できたこと」に目を向けてほめる
- 必要に応じて、医師の治療や薬のサポートも検討する
ADHDは「治す病気」ではなく、「特性に合った環境で能力を活かす」ことが大切です。
📚 ADHDを深く知り、支援につなげるおすすめ書籍3選
ADHDについての理解を深め、子どもや大人の「生きづらさ」への支援を考えるうえで役立つ書籍を3冊ご紹介します。いずれも2025年8月現在、購入可能なものです。
① ADHDといっしょに!自分の強みがわかって自信がつく60の楽しいワーク
ADHDの特性を「弱み」ではなく「強み」としてとらえる考え方(ストレングス・ベースアプローチ)に基づき、子どもが楽しみながら自己理解を深められるワークブックです。
本文で紹介した「ADHDと共に生きるための支援方法」の中で触れた“見える化”や“肯定的な関わり”を実践するツールとして最適。親子や支援者と一緒に取り組むことで、自己肯定感も育まれます。
② マンガでわかる 私って、ADHD脳!?
日常生活で感じる「困った!」を、ユーモアを交えたマンガで紹介。診断を受けた著者本人が、自らの体験と気づきをマンガでわかりやすく描いています。
ADHDの「不注意」や「衝動性」が実生活でどう影響するのか、より具体的なイメージがつかめます。大人の当事者にも、家族や職場の支援者にも読みやすい一冊です。
③ もっと話を聞いてほしいんだ – ADHDの子どもたちが大人に伝えたいこと
ADHDのある子どもたちへのインタビューをもとに、「何を感じ、どうしてほしいのか」を大人に伝える一冊です。子どもの声を丁寧に拾い、大人との関係性のあり方を問いかけます。
「支援者が“できたこと”に注目する」大切さを実感できる構成。子どもの視点を理解することで、日常の関わりが大きく変わるヒントが得られます。
まとめ
ADHDは、困りごとの原因になるだけでなく、視点を変えればその人にしかない力でもあります。
社会の中でそれぞれが自分らしく生きるために、理解と支援の輪が広がることが何より大切です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
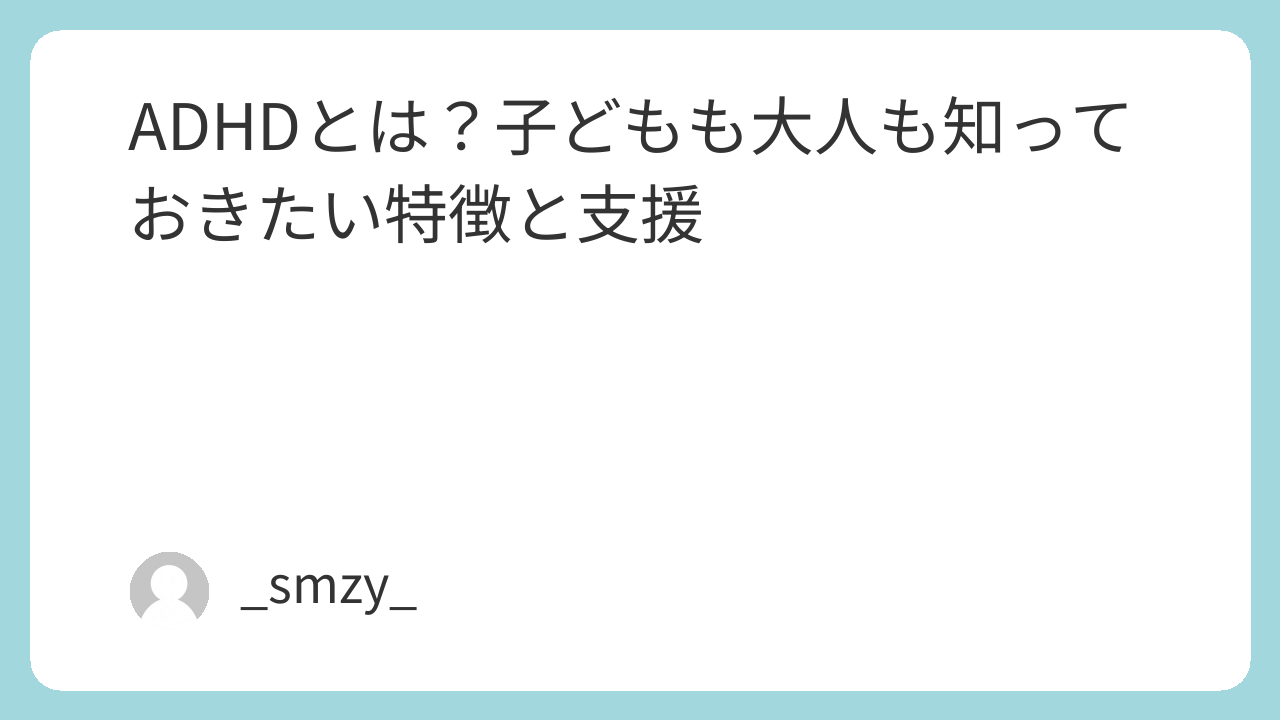
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ac02a39.0a3e2346.4ac02a3a.9c6d759c/?me_id=1213310&item_id=21309557&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5701%2F9784491055701_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ac02a39.0a3e2346.4ac02a3a.9c6d759c/?me_id=1213310&item_id=18345822&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2722%2F9784804762722.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ac02a39.0a3e2346.4ac02a3a.9c6d759c/?me_id=1213310&item_id=21329359&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6098%2F9784491056098_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
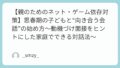
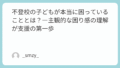
コメント